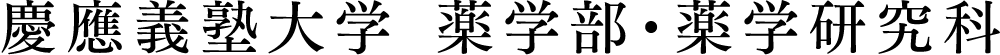センターの目的
創薬研究センターは、創薬を中心とする分野において、慶應義塾内外の関連する研究機関等と密接に協力しながら、創薬研究の成果を広く社会に還元し、健康長寿社会の発展に寄与するとともに、創薬分野における優れた国際的人材の育成を目的とする。
センターの役割
創薬研究センターは、薬学部および大学院薬学研究科の有する機能を結集し、国内外の研究機関、政府機関、企業、関連団体等との研究協力、共同研究プロジェクトの推進を通じた創薬研究コンソーシアムの構築を目指し、次の事業を行う。
- 研究プロジェクトの設置
- 知的財産権の取得、ならびに、技術移転の促進
- 塾生の研究活動支援
- その他、センターの目的達成のために必要な事業
センター長ご挨拶
創薬研究センター長 有田 誠(薬学部長・代謝生理化学講座 教授)
創薬研究センターの目的は、創薬の先導者たる人材育成と産学連携による社会貢献です。薬学部内に新たに研究スペースやインフラの整備を図り、運営体制を強化しています。各プロジェクトでは薬学部専任教員がリーダーとなり、産学連携のプラットホームとして先端的な創薬モダリティや基盤となる技術開発に取り組むコンソーシアムを構築しています。慶應薬学の研究者は、産学連携のパートナーとして高いクオリティと存在感を示しています。また、センターでの研究活動を通して、質の高い創薬マインドを兼ね備えた将来世代の育成に努めています。創薬研究センターへのご理解・ご支援をお願いいたします。

薬学部長
創薬研究センター長
有田 誠
(薬学部 代謝生理化学講座 教授)
研究プロジェクト
創薬研究センターは、慶應義塾大学薬学部の産学連携の場として、複数のプロジェクトが関わり合うことでイノベーションを生み出し(オープンイノベーション)、研究成果を社会に還元するとともに、さまざまな知の融合を通して世界で活躍する人材を育てていく(高度人材育成)という使命を持っています。そのため、各プロジェクトの遂行・協働に必要な環境作りに励んで参ります。また、積極的な異分野交流を図りたいと考えておりますので、多様な知識・技術を持った国内外研究員・企業研究者等の参画をお待ちしております。
ナノ医薬・分野横断遺伝学講座
Division of Interdisciplinary Genetics and Nanomedicine; DiGNa
近年、体液中の微量な核酸分析技術が飛躍的に向上しており、これを用いると、従来の血液検査などと比べて遥かに膨大な情報が、低侵襲で得られることがわかり、いわゆる「リキッドバイオプシー」技術として医療現場への応用開発が進んでいます。私たちは、特に細胞外小胞とそこに含まれるsmall RNAに注目し、最新の遺伝子工学やビッグデータ解析技術も活用して、新たな診断ツールや治療法の開発を、複数の大学や医療機関、企業と共同で進めています。
専任教員:教授 松﨑 潤太郎
創薬メタボローム研究プロジェクト
Innovative Metabolomics Center for Drug Discovery;iMeC
創薬メタボローム研究プロジェクト(iMeC)は、最先端の質量分析技術を揃えたオープンイノベーションの研究環境を整え、創薬シーズの探索・評価、新技術開発および人材育成の場とすることを目的としています。本プロジェクトでは、分析対象に応じて最適化されたメソッドを構築し、生体制御に関わる代謝ネットワークの解明、新しい生理活性物質や創薬標的の探索、医薬品の薬効や体内動態などのメカニズム解明など多岐にわたる病態・バイオロジー研究への応用を目指します。
プロジェクトリーダー:教授 有田 誠
プレシジョン・メディシン分子診断プロジェクト
Project of Precision Medicine and Molecular Diagnostics;PreMo
プレシジョン・メディシン分子診断プロジェクト(PreMo)は、新規に開発される次世代シーケンサーをはじめとする分子診断システムの性能評価について薬学部の持つ分析化学的技術や経験に基づき遂行します。薬剤に関する知識を生かした分子診断の検査結果から投薬等の治療方針決定を行うプロセスについて内容を検討し、課題の抽出や支援方法の開発を目指します。
プロジェクトリーダー:教授 花岡 健二郎
抗体免疫先進研究プロジェクト
Progressive Research for Immunology and Antibody;Primab
抗体免疫先進研究プロジェクト(Primab)は、希少難治性疾患や慢性炎症疾患などに対するアンメッドメディカルニーズに応え、健康長寿社会の実現に貢献することを目的としています。新規抗体医薬の技術開発とシーズ探索を実施するとともに、創薬分野における優れた人材の育成を目指します。
プロジェクトリーダー:教授 長谷 耕二
プレスリリース・ニュース