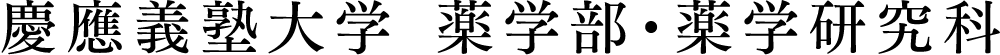2024年度
【海外アドバンスト実習】
アイオワ大学 2024年9月9日~10月4日
大本 真帆(薬学部薬学科6年*当時)
アメリカ・アイオワ大学病院での4週間にわたる実習に参加し、日本と異なる医療制度や薬剤師の役割を実際に体験する貴重な時間を過ごしました。初週には地域薬局の見学を通じてアメリカの医療制度や薬局業務の概要を学びました。残りの3週間は、アイオワ大学病院の急性期病院、抗凝固薬クリニック、精神科クリニックで、薬剤師としての専門的な業務にそれぞれ1週間ずつ参加しました。
アメリカの薬剤師は地域薬局から急性期病院まで幅広い場面で活躍しており、日本の薬剤師とは異なる役割が多いことを実感しました。地域薬局では医療費の高さからOTC薬やサプリメントを利用する患者が多く、薬剤師が相談に応じています。また、薬剤師がワクチン接種の資格を持っており、薬学生も実習中にワクチン接種を経験していました。急性期病院では薬剤師がチーム医療に積極的に参加し、医師と共にラウンドを行って患者の薬物療法を支援しています。さらにファーマシーテクニシャンという薬剤師を補助する職種の方がいるため、薬剤師はより専門的な業務に集中できる体制が整っているのも印象的でした。また、日本の薬剤師が広範囲の業務を担当しているのに対し、米国の薬剤師は特定分野に特化しています。たとえば抗凝固薬クリニックでは薬剤師がPT-INR測定やワルファリンの用量調整を行い、患者が自己管理できるよう支援しています。精神科クリニックではPDMPという電子システムを活用してオピオイドなどの高リスク薬を管理し、乱用防止にも努めていました。
英語での実習は難しさもありましたが、アイオワ大学の先生や学生たちが親切にサポートしてくださったおかげで、充実した実習を過ごせました。プライベートでもアイオワの学生たちとフットボール観戦、リンゴ狩り、日本食パーティー、シカゴ旅行などを楽しみ、4週間があっという間に感じられるほどでした。このプログラムでアメリカの病院実習を経験できたことは私にとってかけがえのない財産であり、後輩の皆様にもぜひ挑戦してもらいたいと思います。


アイオワ大学 2024年9月9日~10月4日
田中 爽乃(薬学部薬学科6年*当時)
私はアイオワ大学で4週間の実習を行いました。薬剤師を進路に持つ身として、日本と海外の薬剤師の役割の違いを学び、薬剤師や薬学、医療に関する幅広い視野を身につけたく、このプログラムに応募しました。
1週目は、私たちに向けた米国特有の保険制度や薬剤師に関する内容の授業、アイオワ大学の学生が受けている授業の聴講、地域薬局の見学等を行いました。2~4週目は病院やクリニックでの実習でした。病院実習は、実習中の学生に付いていく形で参加しました。
実習を通して最も印象的だったことは、現地の学生の実習に対する主体的な姿勢です。彼らは"Student Pharmacist"という肩書のもと、指導薬剤師からほぼ独立して薬剤師業務を行っていました。学生たちが行っていた業務は例えば、患者との対面および電話でのコミュニケーションや電子カルテへの記入などでした。米国の学生の知識の豊富さと、それに付随するまるで一人の薬剤師のようなふるまいに感銘を受けました。一方で、在宅医療や学校薬剤師などの地域密着型の活動は米国では日本と比較して盛んではなく、日本の良さを再認識することにもつながる実習となりました。
放課後や週末は、大学職員の方々が私たちの1か月間の滞在を充実させるための手厚いサポートをしてくださり、毎日楽しい時間を過ごすことができました。異国の文化や人との交流も本実習の目的の一つだったので、新たな発見や刺激がたくさんあり、充実した1か月間となりました。また、アイオワの人たちは本当に優しく、心温まる日々で、先生方や現地で作った友人たちには感謝してもしきれません。
私は追加募集で本実習に応募しましたが、最初から応募していなかったことを後悔するくらい、有意義で貴重な経験となりました。都会の喧騒からはかけ離れた、落ち着いた地での生活もまた東京では味わうことのない素敵な思い出となりました。ぜひ多くの方に挑戦していただきたいと強く思います。


アイオワ大学 2024年9月9日~10月4日
三井 直子(薬学部薬学科6年*当時)
私はアイオワ州にあるアイオワ大学で4週間の研修を経験しました。私は幼少期海外に在住経験があり、その時に学んだことが今の自分に多く活かされていると感じ、今回も海外の医療について自分の目で、肌で、感じたいという思いから本プログラムへの参加を決意しました。
合計4週間のプログラムの中で、現地の授業への参加や薬局見学、在宅医療施設への訪問、病院実習など多くの経験をさせていただきました。特に病院実習では実際に現地の学生と一緒に行動させてもらい、薬剤師として何が求められているのかについて改めて考えさせられました。アメリカには薬剤師の他にテクニシャンと呼ばれる方が多く働いており、調剤業務は全てテクニシャンの方が行うため、薬剤師は基本的に対人業務に注力することができます。そのため、患者さんへのフォローアップや医師との話し合いにより多くの時間を割くことができていると感じました。またもう1つ今回の実習を経て、強く感じたことは現地の学生のレベルがとても高かったことです。日本での実習は、指導薬剤師の方が隣にいるのが当たり前で、何か起こった時は必ず誰かが助けてくれる状況下で実習を行っていましたが、アメリカでは指導薬剤師という存在はいますが、基本的に患者さんの対応から医師との話し合いまで全て学生が独立して行っている場合が多く、とても驚きました。特に急性期の病棟実習では、早朝の病室訪問から参加し、その後のチームミーティングにおいては薬に関する幅広い質問に対して学生が躊躇することなく意見を述べていました。このように学生の頃から責任ある業務を経験することで、より質の高い実習になると感じました。
今回のプログラムでは実習だけではなく、多くの学生や教員の方が放課後の時間や休日に私たちを様々な場所に連れて行ってくださり、アメリカの文化を体験することができました。4週間という短い期間ではありましたが、アイオワという自然豊かで、居るだけで幸せになってしまうような街で、多くの心優しい素敵な方々と出会い過ごした日々は、今後一生忘れることのない宝物になりました。


アイオワ大学 2024年9月9日~10月4日
吉田 菜桜子(薬学部薬学科6年*当時)
私は、アメリカのアイオワ大学で4週間の実習に参加しました。アメリカと日本の医療の違いを学び、その背景にあるアメリカの文化や特徴、医療従事者や患者の考え方に現地で触れてみたいと思い、海外アドバンスト実習に応募しました。
1週目は薬学生の授業への参加や地域薬局の訪問をおこない、残りの3週間は現地の薬学生とともに病院実習に参加しました。アメリカのチーム医療を学ぶ中で、日本と比較して医療従事者の役割が非常に細分化されていると感じました。特に、アメリカにはファーマシーテクニシャンをはじめ、日本には存在しない職種が数多くあります。そのため、各職種が専門分野に専念し、専門外の業務を他職種に委ねる体制が整っていました。患者一人に対して全職種が大きな役割を担い、それぞれの専門知識や強みを生かしてチームに貢献する姿は、日本が目指すチーム医療の形に近いのではないかと感じました。
また、現地の薬学生も医療チームの一員として患者の治療に大きく貢献している姿を目の当たりにしました。薬剤師がいない状況下でも、医師と議論を交わしながら薬学的なアドバイスをおこなう薬学生の姿が非常に印象的で、そのレベルの高さに圧倒されました。今回の実習は、日本の医療や薬学生の在り方について、自分自身の考えを見つめ直す貴重な機会となりました。
海外に住んだ経験や留学経験のない私にとって、今回の実習は大きな挑戦でした。現地では言葉の壁に何度も直面しましたが、現地で出会った先生方や薬学生、友人、そして一緒に参加した慶應生の仲間3人に助けられ、1ヶ月間の実習を充実したものにすることができました。この実習で得た経験や交流を踏まえ、参加して本当に良かったと感じています。


ノースカロライナ大学 2024年9月9日~10月4日
芝 沙織(薬学部薬学科6年*当時)
私はアメリカのノースカロライナ大学チャペルヒル校で4週間の病院実習を体験しました。私は5年次の日本での実務実習を通して日本の医療制度の課題について興味を持ち、アメリカにおける薬剤師の業務や医療制度について学習し国際的視野を獲得することで新たな改善点に気付けるのではと考え、本プログラムに参加しました。
実習を通して、薬剤師の業務の幅と医療保険制度について日米間に大きな違いがあることに驚きました。アメリカではファーマシーテクニシャンや自動調剤システムが主な対物業務を担い、薬剤師は調剤監査や処方監査に時間を費やしていました。対人業務の充実化を推進する日本での必要な取り組みを考えるきっかけとなりました。民間医療保険が主流で、加入する保険では最適な治療薬が保険適応にならずその治療を受けられない患者がいらっしゃいました。薬剤師は他職種と連携しながら経済的負担を考慮した提案が必要なことを学ぶと同時に、皆保険制度をもつ日本では平等に最適な治療を受けられることが強みであることを再認識しました。また、医療事故を防いだ症例 "Great Catch"を病院内で紹介し、医療従事者を称賛する光景を頻繁に目にしました。これはミスの積極的な指摘や薬剤師間の信頼関係の構築につながると感じ、自分自身も共に働く仲間の良き行動を吸収する姿勢を大切にしたいと思いました。
実習後や週末には、ノースカロライナ大学の薬学部生や他国の交換留学生と一緒にアメリカンフットボール観戦やショッピング、コンサートなどに行きました。交流する中で、どの国の学生も一人一人が強い意志を持って薬学部に進学し努力していることに気づき、各国の教育は異なりますが薬学部生としての志は世界共通であると実感しました。
私は日本の実務実習で感じた疑問を動機として本プログラムに参加し、医療従事者側として医療施設に入って薬学的知識を学ぶことができました。このような貴重な経験は本プログラムならではだと思いますので、興味を持った方は臆せず是非挑戦してほしいです!


ノースカロライナ大学 2024年9月9日~10月4日
武田 彩海(薬学部薬学科6年*当時)
私は、アメリカのノースカロライナ大学で4週間の海外アドバンスト実習に参加しました。私は、大学卒業後は博士課程に進学し、臨床の現場における患者さんの治療の選択肢を広げる一助となりたいと考えております。その実現のためにも日本のみならず、海外において臨床の現場ではどのような医薬品が必要とされているのか、という点を重視し、海外の臨床現場の実情や医療システムを学ぶために留学に臨みました。
実習を通して、実務実習で経験した日本の医療についてとアメリカの医療制度や患者さんが抱える問題等の違いに驚く日々でした。最も驚いたことは社会保険システムの違いです。留学前でも、アメリカの医療システムは非常に複雑であることや医療費が非常に高いことなどは知識としてありました。しかし、実際にその複雑さゆえに様々な背景から医療保険に加入できず、受けるべき治療を受けられない患者さんがいらっしゃる、という問題やこのような問題に対してどのような支援制度が存在するのかという点に関しては海外の医療現場で実習をすることで実際に目にし、初めて深く理解することができました。
このような臨床現場における多くの違いから、現地の薬学部の学生が大学でどのようなことを学んでいるのかという点に関しても興味が沸きました。今回のノースカロライナ大学での留学プログラムは1週目から4週目までの4週間は全て病院実習を行うというプログラムでしたが、今回の海外アドバンスト実習を通してできた現地の友達に、授業に出たいという旨を相談したところ、友達がたくさん取り計らってくれ、病院実習に影響が出ない時間帯の授業に参加することができました。授業ではアメリカの社会保険制度に関して学び、アメリカの医療制度の実態や問題点、それを克服するためにアメリカがどのような地域医療や医療制度を目指しているのかを学ぶことができました。
また一方で、アメリカの薬剤師の職務は日本と比較し非常に先進的であるという考えも、留学前はありました。しかし、実際は必ずしもそのようではなく、上記のような社会医療制度の違いによって生じる職務内容の違い以外は私たちが実務実習で経験した職務と同様のものが多いと感じました。現地の薬剤師の方々から「日本の方がきっと医療や医療機器は発展してると思うけど、」という言葉も何度か耳にしました。このように、私が勝手に抱いていたアメリカの医療という想像をいい意味で打ち砕くことができたことも非常に良い経験だと思います。
1ヶ月間は長いようで非常にあっという間の期間でした。海外の病院での実習はその国の医療や制度を学ぶことができるとともに、その国の文化を理解するということに繋がります。このことは机上の知識のみでは決して得ることができない学びです。海外アドバンスト実習は非常に得難い機会だと思いますので、現地で学びたいことは積極的に挑戦してみてください。先生方もそのようなことは快く受け入れてくださいます。また、現地で出会った友達との交流もかけがえのない思い出です。ぜひ、海外アドバンスト実習に参加し、様々な知見を広げていただければと思います。


フロリダ大学 2024年9月9日~10月4日
河村 莉奈(薬学部薬学科6年*当時)
私は、フロリダ大学で4週間にわたり実習させていただきました。実習内容は主に、薬学部の授業への参加、病院やクリニックなど各機関の見学でした。
薬剤師主体のクリニックでは、薬剤師が患者情報の聞き取りから、フィジカルアセスメント、用量調節などの今後の計画を立て、医師と情報共有していました。医師は診断、薬剤師は薬物管理・服薬指導と役割分担がしっかりと行われており、薬剤師の役割や責任について改めて考えることができました。病院では、医師、薬剤師、作業療法士など医療従事者が同じ部屋に在室し、医療従事者間のコミュニケーションが多い印象でした。また、ヘルスケアシステムの違いも実感しました。本実習を通して、様々な面での薬剤師の役割を知ることができ、多職種連携や患者中心の医療を実践したいと思いました。
実習以外にも、アメリカンフットボール観戦、自然公園、食事など多くの場所に連れて行っていただき、フロリダ特有の文化を感じることができました。
私は英語力に自信がなく、日本語が通じない場所で1ヶ月間過ごすことに不安を感じていました。しかし、日常生活においては、大学の先生や学生が常に気にかけてくださり、安心して過ごすことができました。また、実習においても、私の伝えたいことを理解しようとしてくださり、分からないことがあると分かるまで説明してくださいました。
海外の大学・医療機関で薬学を学び、薬学教育や医療制度の違いについて議論できたことは、とても貴重な経験になりました。本実習に挑戦して良かったと思っています。少しでも興味のある方は、是非挑戦してみてほしいです!


フロリダ大学 2024年9月9日~10月4日
中村 茉里奈(薬学部薬学科6年*当時)
私はアメリカ・フロリダ州のフロリダ大学に4週間滞在し、フロリダ大学の薬学教育とアメリカの医療制度について学ばせていただきました。フロリダ大学が有するいくつかの病院・薬局での見学を通して、アメリカと日本の薬剤師の役割の違いについて学び理解を深めることができました。
この実習を通して最も印象に残っているのは、アメリカの薬剤師が自立して働く姿勢です。今回、様々な施設で薬剤部を見学させていただきましたが、どの施設でも医師をはじめとする医療従事者との信頼関係の中で、意見を堂々と発し自分の役割を全うする薬剤師の姿を見ることができました。また実務実習中の学生とも交流する機会があり、彼らの患者さんと話す姿や、他医療従事者と接する姿はとても自立しており、積極的に学ぶ意思を感じました。そんな薬剤師を育成するための薬学教育は、日本に比べ実践的で臨床的であったように感じます。
実習以外でも、日本に来ていた交換留学生とフロリダで再会したり、現地の薬学生と仲良くなりご飯を食べに行ったりすることもでき、多くの貴重な経験ができました。滞在していたアパートのルームメイトとも沢山の交流ができたおかげで、日常生活を不自由なく送ることができ、学年や国籍を超えた人との出会いに感謝しています。
日本での実務実習を終え、日本の薬剤師制度をよく理解した6年生のこの時期だからこそ、得られることの多い実習だったと感じます。将来薬剤師として働く人はもちろんのこと、そうではない人も、異国の医療制度を通して文化の違いを学ぶことは、かけがえのない経験になると思います。


コンケン大学 2024年9月9日~10月11日
井上 真理(薬学部薬学科6年*当時)
海外の医療体制や薬学教育、薬剤師の働き方を自分の目で見て学びたいと思い、海外アドバンスト実習に応募し、タイのコンケン大学にて5週間に及ぶ実習に参加しました。
実習では、主にがん病棟で薬剤師さんと一緒に患者さんの状態や副作用のモニタリングを行ったり、ケースディスカッションやJournal clubに参加したりしました。他には、現地の薬学生と一緒にがんの講義へ参加したり、薬局を見学したり、タイの伝統医学について学ぶ機会がありました。実習後や週末は、現地のタイの薬学生が地元のレストランや観光地に連れて行ってくれ、現地の文化や食事を楽しみました。
5週間の実習を通して、活発なケースディスカッションや薬学生の豊富な知識に驚き、自分自身も刺激を受けました。病棟では、日々、世界共通のがんのガイドラインや臨床試験の論文のデータをフル活用したディスカッションが展開されており、はじめはついていくのが大変でしたが、薬剤師さんがサポートしてくださり、たくさんの学びを得ることができました。また、薬学部の講義や実習は、ディスカッションやプレゼンテーションの機会が豊富で、日本よりも学んだ知識をアウトプットする機会が多いと感じました。そして、実習の機会も2000時間以上確保されているのがタイの薬学教育の特徴です。能動的な授業を通して、知識を実践的に活用し,薬剤師として疾患を判断し,薬を選べる判断力を養っていました。実習を通してタイの強みを知ると同時に、誰でも同じ医療を受けられる日本の医療体制の強みや2年間の研究の機会がある日本の薬学教育の強みに気づきました。
日本を離れて1カ月以上過ごすのは初めてで、慣れない地での実習に不安もありましたが、現地でしか得られない学びは多く、視野も広がりました。少しでも興味がある方はぜひ参加し、たくさんのものを吸収してほしいと思います。


コンケン大学 2024年9月9日~10月11日
坂本 優(薬学部薬学科6年*当時)
タイ王国のコンケン大学にて 5 週間の実習に参加しました。主に大学病院のがん病棟でシャドーイングやケースディスカッションを行いました。また、コンケン大学の薬学生と共に、薬物治療学の講義を受け、タイの伝統医療も体験しました。
実習を通して、保険制度の違いによる治療法の選択をする場面に多く出会いました。タイには、30 バーツ (約 120 円) で一般的な治療を受けられる保険と、政府が全額負担する保険等があります。特にがん治療においては選択できる治療法に差が出ると感じ、誰もが平等に医療を受けられる日本の良い点に改めて気づくことができました。
薬学教育の違いについても実感しました。タイの学生は日本の倍以上の 2000 時間を実務実習に費やしており、薬局では、薬学生が患者へのカウンセリングを通じて適切な医薬品を提案している姿を見て、彼らが実践的な知識を持ち合わせていることに感銘を受けました。
放課後や休日は、日本に交換留学生として来ていたタイの学生達と、屋台やショッピングモール、お寺に行ってタイの文化を学びました。日本では実家暮らしのため、いきなりタイでの一人暮らしデビューとなりましたが、タイの友達や、大学の国際交流担当の方にサポートしていただきながら無事 5 週間を終えることができました。
タイでの実習は英語のほかにタイ語という言語の壁がありますが、向こうで出会ったすべての人は親切で、日本の文化にも興味を示してくださいました。英語環境を求めて参加を決めた海外アドバンスト実習でしたが、コンケン大学で実習をする機会をいただき、自分の想像以上の経験を得ることができたので、参加して良かったと心から思っています。
このプログラムに少しでも興味のある方は、ぜひ挑戦してみて欲しいと思います。


コンケン大学 2024年9月9日~10月11日
田村 史華(薬学部薬学科6年*当時)
タイのコンケン大学にて5週間の実習を行いました。私は他国の医療現場に触れることで日本の医療との違いを学びたいという想いから海外アドバンスト実習を志望しました。中でも、コンケン大学は実務実習で学ぶことの出来なかった「がん」に特化した実習を行っており、国際的な知識も得ることができると感じたため選択しました。
実習では、1~4週目は主に腫瘍病棟で実習を行い、現地学生の授業にも参加しました。5週目は、病院内の薬剤部、TDM、緩和病棟などの見学を行いました。また、コンケン病院ではタイ伝統医療を体験し、付属薬局では地域薬局の役割を学びました。
実習を行った腫瘍病棟では複数の薬剤師が常駐し、ディスカッションや抄読会も多く行われていました。タイではテクニシャンが調剤を行うため、日本よりも患者さんや他職種とコミュニケーションをとる機会が多く、薬物治療の管理に特化していました。実習を通して、国際的でより深い薬物療法の知識を得ることができました。
また、日本とタイの医療制度の違いも学びました。国民が同じ医療を受けられる日本とは異なり、タイでは医療保険の種類によって使用できる薬剤が異なります。そのため、保険によって第一選択薬を使用できない場面が数多く見られ、日本の良さを再認識することができました。一方、薬局では公的医療保険の患者を対象に一般的な薬を30バーツで提供する制度が整い、簡易的な検査や予防接種も提供するなど、タイの薬局の役割の大きさに驚きました。
放課後や休日は、コンケン大学の学生や先生方、腫瘍病棟の薬剤師の方々と食事や観光を楽しみました。タイの方々は、とても親切で温かく迎えて下さり、お互いに第2言語でのコミュニケーションでしたが、毎日楽しく快適に過ごすことができました。貴重な実習の機会を頂けたこと、素敵なタイの方々に出会えたことに感謝してもしきれません。
是非、多くの方にコンケン大学での実習にチャレンジしてみてほしいと思います!


2023年度
【海外アドバンスト実習】
アイオワ大学 2023年9月11日~10月13日
齊藤 里菜(薬学部薬学科6年*当時)
アイオワ大学にて5週間の海外アドバンスト実習に参加しました。
実習では、最初の1週間は薬学生の授業への参加や地域薬局・在宅医療に関わる施設などを見学し、残りの4週間は病院での実習を行いました。その中で、「チーム医療」とは何か、またチーム内で薬剤師が果たすべき役割が何かを肌で実感しました。アメリカではファーマシーテクニシャンの制度が整っており調剤をする薬剤師と病棟薬剤師は完全に分かれているため、病棟や医療チームの中に常に薬剤師がいることが当たり前になっています。ラウンド中にもオフィスにいる時にも、何度も医師が薬剤の投与量はどうすべきかなどを相談にくるのを目にし、常に医療者同士が相談できる体制が整っていることの良さを感じました。また、薬学生が1人で患者さんとお話しをしながら患者さんに合わせて会話を引き出していく姿や彼らの知識レベルの高さに感銘を受けました。
授業後や休日には、学生や先生方が様々なアクティビティに連れて行ってくださいました。アメリカンフットボールの試合を観戦した際の強い一体感と高揚感、アイオワの人々の温かさは日本では経験することができない貴重な経験だったと思っています。
英語での病院実習ということで難しいことも理解が追いつかないこともありましたが、周りの皆さんがいつでも優しくサポートしてくださいました。海外の医療について、医療者の立場から体験することができるのはこのプログラムならではであり、さらに、実際に目で見ることでしか分からないものだと思います。挑戦して良かったと心から思える経験になりました。ぜひ多くの学生に興味を持っていただけたら嬉しく思います。

アイオワ大学 2023年9月11日~10月13日
中西 りさ(薬学部薬学科6年*当時)
私はアメリカ・アイオワ州のアイオワ大学にて5週間にわたり実習をさせていただきました。日本と海外の医療の違い、海外の臨床現場におけるニーズ、海外の薬学生の考え方などを現地で直接学びたいと思い、海外アドバンスト実習に応募しました。
アイオワ大学では1週目に講義の受講・地域薬局の見学、2週目から5週目までは病棟及びクリニックで実習中の現地の学生に付く形で1週間ずつ実習を行いました。
アイオワ大学の薬学生は薬剤師から独立して業務を行う形で実習を行えていたほど臨床に関する知識が深く、多様な視点を持っていたことに驚きました。処方設計に携わる機会が多いことから適切に必要な情報を収集・吟味・提供する能力が非常に求められており、改めて薬剤師が担っている責任を再認識しました。英語で疾患や治療について話すことが難しい時もありましたが、薬剤師及び学生の方々がいつも優しく丁寧に教えてくださり、また私の話を聞いてくださったことが印象に残っています。相互に情報交換・意見交換を活発にできる場があり、その中で多くの気付きもありました。
本プログラムに参加したいと長く思っていたものの、日本語が通じない場所で約1か月間生活し勉強するにあたり不安も大きく、参加することは私にとって大きな挑戦だったと思います。しかし、本大学及びアイオワ大学の担当者の方々が留学前から手厚くサポートしてくださり、アイオワ大学の学生、前年度参加した先輩方、今年度私と同じように参加した同期の協力や支えもあり、非常に充実した楽しい時間を過ごすことができました。参加することを迷われている方にはぜひ挑戦していただきたいと強く思います。何にも代えがたい経験が得られるはずです。


ノースカロライナ大学 2023年9月11日~10月6日
梶原 ひかり(薬学部薬学科6年*当時)
私はノースカロライナ大学に4週間滞在し、3週間の病院実習と、1週間の薬学部の授業を体験しました。実習では、毎日異なる部門の薬剤師をシャドーイングし、臨床薬剤師や中央業務の薬剤師の働き方を学びました。
臨床薬剤師のシャドーイングでは、毎朝ラウンドに参加しました。医師、薬剤師、看護師から成るチームで10数人を担当しており、まず医療従事者で患者の状態や治療方針を話し合った後、ベットサイドで患者や家族と話していました。ラウンドでは、医師からの薬に関する質問にすぐに答え、また医師に治療に関する質問をして積極的にディスカッションをしており、アメリカ薬剤師の専門性や薬剤師に対する信頼性の高さが印象に残りました。アメリカの薬剤師はスペシャリストな働き方をしており、専門分野に関しては知識が豊富で驚きました。その反面、ジェネラリストな傾向の日本の薬剤師の方がより広い範囲の知識があり、アフリカのような途上国では日本の薬剤師の方が活躍できるという話を聞き、両国の薬剤師のメリットデメリットに気付くことができました。今回学んだことは将来に役に立つと思いましたし、必ず仕事で活かしたいです。
放課後や休日は、交換留学生やその友達とスポーツ観戦や食事をしたり、寮でできた友達と音楽フェスティバルやショッピングに行きました。1ヶ月間という短い期間でしたが、アメリカの大学生活を思う存分満喫しました。たくさんの友達や思い出ができ、かけがえのない素晴らしい経験になったと思います。
私は英語力に自信がありませんでしたが、現地の皆さんはとても優しく、分からないと伝えれば分かりやすく説明してくれましたし、私の話も親身に聞いてくれました。何事も楽しむと、その姿勢は伝わると思います。積極的に参加することをお勧めします。

ノースカロライナ大学 2023年9月11日~10月6日
関 智羽(薬学部薬学科6年*当時)
私は、米国のノースカロライナ大学で実習を行いました。このプログラムに参加し、様々なバックグラウンドを持つ人たちと意見を交わし合い、視野を広げることの大切さを学びました。米国、日本、どちらの医療制度や薬学教育にも長所と短所があります。薬剤師や薬学生とディスカッションする中で、それぞれの魅力的な部分や改善すべき部分をたくさん見つけることができました。日本にいるだけでは気づけなかったこともたくさんあり、今後も多様なバックグラウンドを持つ人と様々な観点で意見を交わし合って世の中に貢献したいという想いを強くしました。
このプログラムに参加して最も良かったことは、かけがえのない友人がたくさんできたことです。私たちが米国を訪れる2ヶ月ほど前に、ノースカロライナ大学の学生2名が日本で実習を行いました。そのおかげで、米国の学生から見た日本の医療についても意見を聞くことができ、とても有意義なディスカッションを数多く行うことができました。また、私たちが日本を案内した際はとても喜んでもらうことができ、ノースカロライナでは毎週のように遊びに連れていっていただき、どちらもとても楽しい時間を過ごすことができました。米国では他にも多くの方が優しく接してくださいました。帰国後でも交流が続くような交友関係を築けたことは一生の思い出です。
海外の医療機関で実習を行うことはとても貴重な機会なので、興味がある方は積極的にチャレンジしてみてください!海外アドバンスト実習の準備と並行して卒業研究や卒業試験に取り組む必要があるため大変な時期もありましたが、頑張って良かったと心の底から思えるような貴重な経験ができました。何より人として大きく成長できたので、是非多くの人に挑戦して欲しいです!


フロリダ大学 2023年9月18日~10月13日
伊東 香南(薬学部薬学科6年*当時)
フロリダ大学での実習では、様々な医療施設への訪問や薬学部の授業への参加を通し、米国の薬剤師について実践的に学ぶ機会をいただきました。
実習を通して私が一番有意義だと感じたことは、現地の専門家の方々と、日米間の医療や薬剤師の違いについて意見交換をすることができたことです。実際の医療現場を見たうえで議論をすることで、違いの背景にある文化・地理的要因を知ることができました。
また、教育現場と医療現場をどちらも体験できたことで、米国での実践形式やチームワーク重視の教育スタイルが、その後の薬剤師としての職能や働き方に良い影響を及ぼしているという気づきを得ることができました。現地の学生のアクティブに学ぶ姿勢から、私自身も得るものが多かったです。
今回が慶應薬学部からフロリダ大学への最初の派遣であったため、事前情報が少なく、渡航前は現地の生活に不安がありました。しかし、日常生活においては、先生方や学生が常に気にかけてくださり、不自由なく過ごすことができました。食事やダウンタウン散策など、学生の輪に混ぜていただくことで、アメリカの大学生活を楽しく体感することができました。
また、実習の最後には、集大成として大学でプレゼンをする機会も与えていただき、充実感で締めくくることができました。一か月という短い期間の中で実りある実習とするためには、主体性をもって動くことが重要だと感じました。
同じ薬学という領域を専門とする他国の学生や先生方と今後に繋がる関係性を築けることも、海外アドバンスト実習の素晴らしさの1つだと感じています。
実務実習や研究活動を経た段階で参加することに大きな意味があるプログラムだと思います。少しでも興味がある方は、臆せず挑戦してみてほしいです。


フロリダ大学 2023年9月18日~10月13日
諏訪 円佳(薬学部薬学科6年*当時)
フロリダ大学での4週間の実習に参加しました。現地では、病院、薬局、クリニック、研究機関など様々な施設を訪問し、それぞれの場所で活躍する薬剤師の働き方について学びました。特に印象に残ったのは、経済的に問題を抱える患者を主に受け入れるクリニックです。国民皆保険がない米国だからこそある特徴的なクリニックでした。疾患に加えて治療費、医療機関までの通いやすさなど、患者を取り巻く環境にも注意を向けており、患者にとってより最適なサポートをすることができていると思いました。
また、医師、薬剤師、ケアワーカーが同じ部屋で、互いに意見を出し合いながら働いており、職種と立場を超えてフランクに意見交換する環境があり、チーム医療が徹底していました。クリニックで実習中の現地学生も交えてざっくばらんに意見交換をしている姿は日本の実習ではあまり見ることがなかったため、とても新鮮でした。
休日は、現地学生と一緒に出かけ、文化や価値観の違いを楽しみつつ、多くの経験をすることができました。フロリダ州は中南米からの学生も多いため、音楽、食事など多国籍な文化を感じ、毎日刺激的な生活を送ることができると思います。キャンパス内に野生のワニがいるのもスリリングでした。
この海外実習プログラムは海外のヘルスケアシステムの違いだけではなく、他国の文化や日本の実習で経験できなかったことなど幅広い学びを得ることができるためおすすめです。私は卒業研究や就職活動と重なるのではないかと不安な気持ちを抱えて応募しましたが、学生のうちにこのような貴重な機会を頂くことができ、挑戦してみてよかったと強く思います。迷っている方は是非勇気を出して挑戦してみてください。


2022年度
【海外アドバンスト実習】
アイオワ大学 2022年9月6日~10月7日
大上 愛由(薬学部薬学科6年*当時)
私は、アイオワ大学で5週間、海外アドバンスト実習に参加しました。病院内での実習だけでなく、現地の薬学生が受ける講義への参加、薬剤師が携わる様々な地域の施設見学を行いました。
実習を通して得た収穫は大きいです。まず、アメリカの医療の仕組みや薬剤師のあり方についての知識を自分のものにできました。日本とあらゆる点で異なる仕組みが導入されているアメリカの臨床現場を実際に体感すること、医療以外の社会環境や人々の価値観を合わせて学べることにより、「ただ知っている」だけでなく、「自分で考えられる」知識を得ました。さらに、繰り返し体験すること、実際に働いている薬剤師さんから臨床現場の裏側まで聞けることは実習という特性ならではの魅力だったと思います。
さらに、自分のものにできた知識をもとに、医療の仕組みや薬剤師のあり方に関して、モヤモヤしたことも大きな気づきです。薬学部に6年間所属していると、誰しも多かれ少なかれ、医療・薬剤師のあり方に対して、自分なりの意見が持っていると思います。私は、自分の中の意見が徐々にクリアになってきているように感じていて、当初は実習を通して、その意見がより強固になることを期待していました。しかし、実際は、今までの意見が必ずしも正しいとは思えなくなり、逆に頭の中が混乱する結果となりました。この経験を通して、自分は狭い世界で意見を完結させようとしていたことに気づかされ、頭がクリアになってきた時こそ危険であり、自分の視野を広げる努力をしなければいけない時期なのだと学びました。
本実習は、アメリカで薬剤師として働かない限り、長期間、学生という立場で臨床現場の中に入れてもらえるのは、他で経験しようとしてもなかなかできない貴重な機会だと思います。将来の進路や英語の得意不得意等に関わらず、どんな人にもおすすめしたいプログラムでした。


アイオワ大学 2022年9月6日~10月7日
千島 陽奈(薬学部薬学科6年*当時)
私はアメリカ・アイオワ州にあるアイオワ大学で5週間の実習をさせていただきました。
渡航する前から入念に希望を聞いてくださり、コロナ対策が求められる状況にも関わらず、病院、薬局、さらには在宅点滴サービスなど多岐にわたる医療施設を訪問させていただきました。病院実習では薬剤師と薬学生だけでのディスカッションの機会もあり、よりフランクに意見交換をすることができて刺激になりました。アメリカの薬学生は在学中からファーマシーテクニシャンとして働くことができ、その実践力の高さに驚かされました。患者さんの相談に一人で対応する薬学生などを目の当たりにして、日本で薬剤師として働くときは調剤室内での業務のみに甘んじていてはいけないと強く感じました。
また、アイオワの人々のおおらかさも、医療現場の内外を通して印象的でした。さまざまな外見や話し方の人がいて、固定されたものを前提としない文化を感じました。ダウンタウンの店先には路面に絵が描いてあったり、休日には音楽が聞こえたりととても雰囲気が良かったです。また、薬学生の皆さんは本当に親切で、不慣れな私たちに毎日のように町を案内してくれました。
異国の地での実務実習は少なからず勇気の要ることだと思います。私自身、日本語の伝わらない現場で薬剤師の卵としてうまく立ち回れるか心配でした。しかし、外国のことですから知らないことだらけで当然です。途中からはそうしたことを臆せず質問することが最大の学びにつながると気づき、知らないことに直面しただけ儲けものだと思うようになりました。幸いにも、実習では沢山の質問の機会を設けていただきました。是非、少しでも興味があるという人は挑戦してみることをおすすめします。絶対に挑戦して損にはならないと思います!


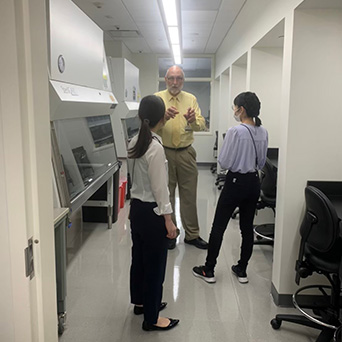
ノースカロライナ大学 2022年9月12日~10月7日
木村 枝里香(薬学部薬学科6年*当時)
ノースカロライナ大学病院で、4週間の病院実習を行いました。実習では病院薬剤部以外にも小児チームや各ICUチームなどの様々な医療チームを見学することができ、病院薬剤師の業務だけでなく、薬剤師と他職種との関わり方についても学ぶことができました。
医療チームのラウンドではチーム全員で患者のベッドサイドを回り、患者を交えて今後の治療方針などを話し合っている様子を見学しました。日本でも患者の意見は重要視されていますが、アメリカでは患者ファーストの姿勢がより徹底されているように感じました。
また、アメリカでは電子処方箋が広く使われており、薬剤師がパソコン上で処方の安全性・妥当性を確認してからテクニシャンが調剤をするなど、ITの活用により効率的に業務が行われていることを実感しました。日本でも電子処方箋が導入されるため、今後の日本の医療現場の変化について考えるきっかけとなりました。
一方で、アメリカには日本のような皆保険制度がないことから、患者の収入などに応じて受けられる医療に違いがあることなどを知り、日本の医療制度の優れた部分を再確認する機会にもなりました。
実習が休みの日はノースカロライナ大学の学生と交流したり、現地のスーパーマーケットや薬局に行ったりと、アメリカの文化を肌で感じることができました。ノースカロライナ大学の学生に野球観戦に連れて行ってもらったりホームパーティーに呼んでもらったりと、友人として接してもらえたことがとても嬉しかったですし、今でも大切な思い出です。
もちろん、卒業研究と並行して実習準備をしたり、専門用語を使った議論を英語でしたりと大変なこともありましたが、それ以上に本実習でしかできないとても貴重な経験が得られました。
私は海外経験が全くなく、語学力やコミュニケーションに不安を持ちながらの実習でしたが、周りの方々の協力もあり無事に実習を終えることができました。もし、興味はあるけど同じように不安があるという方がいたら、ぜひ前向きに挑戦してほしいと思います。


【海外臨床特別研修】
ノースカロライナ大学 2022年9月12日~10月7日
大野 由紀子(薬学専攻博士課程2年*当時)
私が本プログラムに参加したのは、少しでも多くの経験を積んで、広い視野を持った薬剤師になりたかったからです。元々は2020年に渡航予定でしたが、コロナ禍で断念せざるを得ませんでした。しかし、院進して幸運にも再挑戦する機会を頂けました。
私が訪れたのはノースカロライナ大学 (UNC) 病院です。4週間の実習中、ほぼ日替わりで異なる診療科を周り、多くの薬剤師やテクニシャンをシャドウイングしました。
UNC 病院はアメリカの中でも先進的な病院で、国の違いだけでなくレベルの高さからも多くの学びがありました。特に印象的だったのは全外来部門に薬剤師が配置されていた点と、教育や研究に力を入れていた点です。
また、日本とアメリカで出来る業務内容や文化に違いはあっても本質的な部分は変わらないことに気づけたことが実習に参加して一番よかった点です。機械の導入など、日本の薬剤師の業務内容にも変化が訪れていますが、その中でも変わらず、薬の専門家として在ること、他の医療スタッフや患者さんとの向き合い方が大切であると痛感しました。この気づきは卒業後の私の薬剤師としての指針になることでしょう。
本プログラムを希望する方へ、アメリカでは自己主張すること、ポジティブな表現をすることが好まれます。疑問に思うことや自分がやりたいことはぜひ積極的に発信してみてください。そして感謝やポジティブな気持ちをたくさん伝えることをお勧めします。
英語に不安を感じる方も多いと思いますが、準備期間もありますし、最後は「伝えたい!」という強い気持ちを持って言葉を重ねたら意外と何とかなります。得難い機会なので、ぜひ挑戦してみてください。

2021年度
アイオワ大学 2021年9月13日~10月1日
石橋 春奈(薬学部薬学科6年*当時)
アイオワ大学での海外アドバンスト実習は、日本の医療制度や薬剤師の職能を新しい視点で見直し、より深く理解するために非常に有意義な経験でした。
日本で生活する中で当たり前の制度や、薬剤師の働き方が、世界で共通のものではないと学んでいましたが、実際にアメリカの医療現場に伺ったことで、各国の医療の違いには、社会的な背景や文化の差異が大いに関係していると実感することができました。海外の先生や学生と、お互いの環境について教えあい、それぞれの医療制度の課題や、理想的な薬剤師の在り方を議論できる機会は他に無く、海外アドバンスト実習の魅力だと感じました。また、自由時間には、アメリカンフットボール観戦やアイオワ大学の周辺地域の散策などアメリカの文化を体験できたことも、良い思い出になりました。
私は、「失敗を恐れずに積極的に挑戦すること」が海外アドバンスト実習に参加するうえで最も重要であると感じています。私は海外での居住経験や留学経験が無く、語学力に全く自信がありませんでした。しかし、実際に渡航してみると、先生方も学生達も、「完璧な英語で話すこと」ではなく、「私自身の考えを伝えようと努力すること」を期待していると分かりました。最初は緊張していましたが、過ごしていくうちに徐々に会話に慣れ、コミュニケーションをとることが楽しくなりました。この実習に参加したことで、初めて気づいたことや学んだことは渡航前に想像していた以上にとても多くありました。私のように、海外での実習に興味があるが、語学力に不安のあるという方は、ぜひ勇気を出して挑戦してほしいと強く感じています。

アイオワ大学 2021年9月13日~10月1日
坂井 真衣子(薬学部薬学科6年*当時)
私がアドバンスト海外病院実習に参加してよかったことは、大きく分けて2つあります。
1つ目は、海外の医療現場の実情を間近で感じられたことです。私が実習をおこなったアメリカでは、日本よりも薬剤師にできることが多いと感じました。特に印象に残ったことは、薬剤師や講習を終えた薬学生が薬局などでワクチン接種を行っており、新型コロナウイルスのワクチン接種のほとんどを薬学生が行っていたことです。また、ピッキングなどの対物業務はテクニシャンが行い、その分アメリカの薬剤師は対人業務に時間を割くことができていると感じました。私はアドバンスト海外病院実習に参加したことで、5年時の病院実習だけでは機会がなく学べなかったことや、日本と海外の違いも学ぶことができました。
2つ目は、海外の文化を肌で感じることができたことです。私が実習をおこなったアイオワ大学は町の中心地に近く、実習の帰りにカフェに寄ったり買い物をしたりが気軽にできました。また、実習先の大学・病院の先生方や滞在していた家のオーナーには親切にしていただき、休みの日には町の案内やスポーツ観戦に誘っていただくこともありました。3週間の滞在で出会ったすべてが新鮮で、貴重な経験でした。
私がアドバンスト海外病院実習に参加する上で一番不安だったことは英語力でしたが、参加を決めてから実習まで時間があり、実習の前に事前授業もあるため、しっかり準備することができます。また、実習中でも空いた時間に復習などを行うことで、より多くのことを学べたと思います。そのため、少しでも興味があれば参加してみることをお勧めします。きっと、他ではなかなか得られない経験になると思います。



2019年度
ワシントン大学 2019年5月29日~6月28日
木城 美保(薬学部薬学科6年*当時)
ワシントン大学附属病院の1つであるNorthwest Hospital and Medical Centerにて2019年6月に約1ヶ月間の実習に参加しました。渡航前にオンラインで教育プログラムを受講し、「Pharmacy Assistant」(現地の薬剤師の監督のもと、限られた業務を行える資格をもつ)として、救急病棟専属の薬剤師とともに、主に抗菌薬や血液凝固阻止剤といったリスクのある薬の用量、栄養剤に含まれる成分の種類や割合を決定するといった業務を行いました。アメリカは州によって法律が異なり対応が違うため、実習先の要件に合わせて準備が必要ですが、周りの方々のサポートもありますし、準備も含めて良い経験となりました。
日本では薬の用法用量に関して、薬剤師はあくまで医師への「提案」はできますが、決定権はありません。アメリカでは、薬剤師の決定権が日本と比べて大きく、自分が設計した用法用量がそのまま患者さんの治療に直結します。責任は大きいですが、病状が良くなっていく患者さんを見るのは本当に嬉しいですし、医師や他職種と「チーム」として働く一体感を強く感じることができました。
実習は平日の7時から15時までで、実習後や週末はステイ先のホストファミリー、現地の学生達と一緒にシアトルの街を満喫しました。特にホストファミリーは本当に親切な方々で、今でもメールのやり取りをするなど交流があり、素敵な出会いとなりました。
渡航前は語学力や実習内容に関して、自分にできるだろうかと自信が持てず、不安なこともありましたが、ずっと憧れていたプログラムに参加でき、本当に貴重な経験となりました。迷っている方はぜひ、挑戦してみてください!
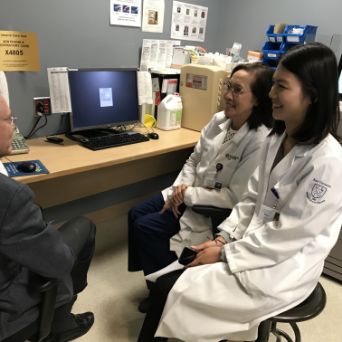

アイオワ大学 2019年9月1日~10月6日
冨沢 佳弘(薬学部薬学科6年*当時)
本記事をご覧になっている皆様、はじめまして。2019年度の海外アトバンスト実習で、米国アイオワ大学へ留学しました冨沢佳弘と申します。私が本プログラムを修了して感じた、本プログラムの特徴や学んだことなどについてお話しいたします。
海外アトバンスト実習の特徴は、ウェブサイト等で紹介されている通り、見学型ではなく参加・体験型の実習であるという点です。実習先の病院では、実際に現地の薬学生と共に医療チームの中に入り、カルテからの情報収集、患者さん・薬剤師等の医療従事者とのコミュニケーションなどを行います。現地の学生や医療従事者と共に行う臨床実習は、非常に刺激的で、勉強になりました。また、プログラムの中では、実習先に渡航する前に、現地のプリセプターを日本に招き、数週間程度の講義を共にする機会もあります。そこでは、海外のガイドラインや医療制度などを事前に学ぶ事ができ、これからお世話になるプリセプターと事前にコミュニケーションすることができたため、海外経験がない自分にとって大きなプラスでした。
海外アトバンスト実習で学んだことは多々ありますが、その中でも特に大きな学びは、国際的な視野を持てた点です。皆様もご存知の通り、日本とアメリカの医療システムはいくつかの点で差異(例えば、Pharmacy TechnicianやPhysician Assistantといった日本にない医療専門職の存在、薬剤師によるワクチン接種など)があります。それらがどのような背景で違っており、結果として患者・患者家族、医療従事者といったステークホルダーにどのような影響を及ぼすのか、理想的な医療提供を実現するためには、日本はどの点を学ぶ事ができるのか、といった点に対して、他国の現状や考え方を知ることにより、自分の視野が拓けた実感があります。製薬業界やヘルスケア業界は、決して日本国内に完結するものではないため、こういった国際的な視野は、仕事をしていく中で特に役に立っています。
最後に、本プログラムに興味を持っている方、応募を迷っている方へメッセージです。本プログラムは全国の薬学部の中でも先端的なプログラムの1つだと思いますし、ここでの約1ヶ月間の経験はかけがいのないものになります。しかし、多くの日本人が「留学」と聞いたときに最初に懸念するのが言語上の問題かと思います(私もそうでした)。特に、医療現場では、対医療従事者向けの専門的なコミュニケーションと対患者向けのカジュアルなコミュニケーションがあり、日本語でも自信のないものを英語でできるのか、と身構えてしまう方も多いと思います。実は海外の臨床実習において、薬学生は既にメリットがあるのをご存知でしょうか。それは、医薬品名(一般名)は世界共通という点です。日本語でも英語でも、高血圧治療薬であるアムロジピンはAmlodipineですし、脂質異常症治療薬のロスバスタチンはRosuvastatinです。もちろん一部例外はありますが、私が滞在先の病院のカルテで見た医薬品はほぼ日本と同じ名前でした。これは医薬品名の知識が豊富な薬学生の特権で、言語上の問題はほぼ解決かと思います。
慶應義塾では、国際担当の教職員の方や海外アトバンスト実習に参加した先輩など、多数の方が皆様をサポートしてくれます。是非とも、参加を検討する中で、様々な方から情報収集し、納得のいく選択をしていただければと思います。私も、一人の塾員として応援しています。

ノースカロライナチャペルヒル校 2019年9月9日~10月4日
山本 響子(薬学部薬学科6年*当時)
米ノースカロライナ大学病院における約4週間の海外アドバンスト実習に参加し、薬剤部のみならず、循環器ICU、新生児ICU、TPN(中心静脈栄養)専門チーム等、多様な診療科の薬剤師業務について幅広く学ばせていただきました。各診療科で毎朝の回診に参加し、ベッドサイドで患者さんの声に耳を傾け、医師・看護師・薬剤師を含む各メンバーがそれぞれの視点から積極的にディスカッションを重ね、チーム一丸となって最適な治療方針を入念に決定していく過程を間近で学びました。このように、チーム医療における活発な多職種連携、他職種からの薬剤師への厚い信頼を肌で感じたことが最も印象に残っています。一方で、医療保険制度や薬剤師の業務範囲等、日米間での医療現場を取り巻く環境の違いを実感し、日本の薬剤師に求められる役割を客観視でき、日本の医療現場の優れた部分にも意識を向けることができました。
実習外の時間では現地の薬学部生と交流を深め、地元住民の健康管理のボランティア活動やチャリティーイベントへ参加したことも忘れられない思い出です。勉強熱心で志の高いノースカロライナ大学の薬学部生と、将来どのように薬学の知識・経験を社会に活かしていきたいかを語り合う中で刺激を受け、自分自身も奮い立たせられたことは、帰国した今でも大きな糧となっています。海外アドバンスト実習で得られたかけがえのない経験を活かし、より良い日本の医療現場に貢献することができるよう日々励んでいます。
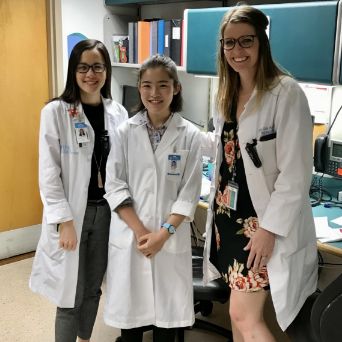

2018年度以前
コンケン大学 2018年9月3日~10月5日
横山 由佳(薬学部薬学科6年*当時)
私は薬学部6年生の時に海外アドバンスト実習に参加し、タイ王国コンケン大学で約1カ月の病院実習を受けました。
実習では、主にコンケン大学付属病院の腫瘍科病棟にて、短期レジデントとしてタイ王国の他病院から研修に来ていた薬剤師やコンケン大学の薬学部生と共に、がん患者ケアを学びました。午前中は、コンケン大学の学生にタイ語を英語に訳してもらいながら患者さんとお話をし、午後にレジデントの方と相談しながらSOAPを作成、発表しました。また、抗がん薬の勉強会、症例報告、論文紹介のプレゼンテーション等にも参加しました。実習中はコンケン大学の学生と交流する機会が沢山あり、学生同士で意見交換ができたことはとても刺激的で貴重な経験になりました。
実習中に特に印象に残ったのは、薬剤師の患者さんに対するきめ細やかな配慮と、幅広い知識を持ち、チーム医療の中で薬の専門家として活躍する薬剤師の姿でした。抗がん薬治療を安全に効果的に行うには多職種連携が重要であると改めて実感しました。
この実習を通して、薬学生として実務実習経験を積むことができただけでなく、自分自身が将来どのような薬剤師になりたいか目標を持つことが出来ました。そして何より、国を超えて沢山の友人や尊敬する先生に出会えたこともこの実習で得た財産だと思っております。
今後も多くの学生にタイでの実習を経験していただきたいです。


ワシントン大学 2017年6月3日~7月5日
土谷 聡耀(薬学部薬学科6年*当時)
私はワシントン大学附属の病院である Northwest Hospital & Medical Center (米国シアトル) を訪ね、同級生と 2 人で 4 週間にわたる集中治療室での病棟業務実習を行いました。
実習では一貫して集中治療室に入院している患者の薬学的管理を行いました。日々入れ替わり、刻々と容態が変化する患者の薬学的管理業務に従事することで多くの知識や技能を身につけ、臨床能力を高めることができました。指導薬剤師である Lee 先生は私たちを新米薬剤師のように扱い、あらゆる業務を行わせてくれました。また、医師や患者と話す機会を積極的に与えてくださり、非常に充実感が高い実習でした。
私は海外アドバンスト実習を通して文化と医療の結びつきを学びました。例えば米国の訴訟社会という文化は抗菌薬の選択に影響していると、感染症内科医の先生が教えてくれました。また、治療費を払えないホームレス患者の入院を拒否する病院が相次いだことから救急外来における入院拒否を禁ずる法律ができたらとのことで、日本特有の文化とは何か、それが医療にどう影響しているかを考える良いきっかけとなりました。
薬剤師の職能改革を重ねてきた米国は薬剤師先進国に見えるかもしれません。しかし実習を経て、決してそうではないと思うようになりました。米国を追従するのではなく、日本の文化や社会情勢に合う制度、日本の薬剤師の長所を生かした制度を追求すべきです。限られた世界に留まっていると自らの文化や特性に対する理解の浅さに気づいていないことすら、私たちは認識できません。ぜひ海外アドバンスト実習に参加して知見を広げてほしいと思います。
(土谷君の体験談は『ファルマシア』Vol. 55, NO. 12, 2019. p1160-1161 に掲載されました)
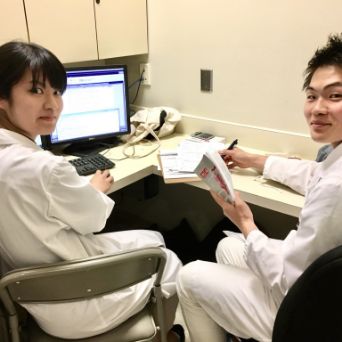
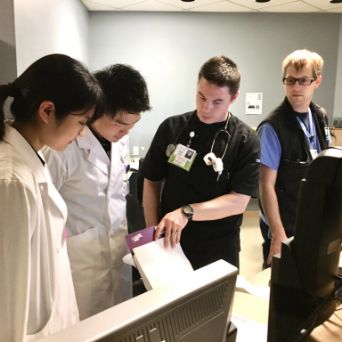
米国食品医薬局(US Food and Drug Administration (FDA))
2018年9月4日~9月28日
難波 祐樹(薬学部薬学科6年*当時)
私は慶應義塾大学薬学部を代表し、2018年にFDA研修に参加いたしました。約1カ月間の研修期間を通じて、主に「米国における医薬品の開発・審査プロセス」、および「FDAから患者さん、医療従事者、企業に対する情報提供の仕組み」について学びました。具体的には、副作用報告に対する電話対応補佐、医薬品開発関連の公聴会への参加、FDA局員による薬学生向け講義への参加、新薬の臨床試験をテーマにした輪講、日本の承認制度・市販後調査に関するプレゼンテーションを実施しました。また、米国の薬学生と同じ土俵で、日々ビジネスやサイエンスにおける専門性の高い議論を行いました。バックグラウンドが全く異なる学生との議論を通じて、文化や視点の違いから生まれる気づきを多く得ることができました。同時に、私自身も自分なりの視点から英語で意見を発信し、討議していく刺激的な時間を過ごさせていただきました。
大学卒業後は新薬開発の世界に進むことを決めていた私にとって、規制当局の視点から医薬品開発に触れることができるFDA研修は、私の将来のキャリアにおいても大きなアドバンテージになることを当時から確信しておりました。そして、現在私は実際にビジネスサイドから新薬開発に関わっております。FDA研修での貴重な経験は、医薬品開発における自身の役割、キャリアの展望を俯瞰的な視点から考えていくうえで、非常に重要な判断指標となっています。
On behalf of Keio University Faculty of Pharmacy, I participated in the Food and Drug Administration (FDA) Pharmacy Student Experiential Program in 2018. Through the training period of about a month, I mainly learned about the "drug development and review processes in the United States (US)" and "how the FDA provides information to patients, healthcare professionals, and the industry."
Specifically, I experienced: shadowing of adverse event report calls, participating in public meetings related to drug development, student lectures offered by FDA staffs, Journal Club presentation of an article about a study of recent FDA approved drug, and a presentation about the approval system and post-approval assessment in Japan. In addition, with the US pharmacy students, I had discussions about highly specialized topics of business and science every day. Through discussions with students from completely different backgrounds, I had a lot to learn from the differences in culture and perspectives. At the same time, I had an exciting time to express my opinions in English from my own perspective.
For me, who had decided to join the industry of drug development after graduating from university, I was convinced from that time that this FDA program, which gives me exposure to drug development from a regulatory perspective, would be a great advantage for my future career. And now I am actually involved in drug development from the business side. These valuable experiences in the FDA program are now a very important indicator for me, in terms of understanding my role in the drug development industry and deciding my career plans from a wider point of view.
海外協定校プリセプターより
アイオワ大学部薬学部
薬学実務実習科長
ジェイ・カリー教授
We look forward to hosting and working with student pharmacists from Keio University Faculty of Pharmacy. Since beginning our exchange nearly twenty years ago, over thirty Keio students have traveled to Iowa to learn about the US health system, pharmacy, and life in the middle of America.
We have developed a unique experience allowing the students to get the feel of an American university while at the same time learning in an environment that is supportive of international visitors' language and educational needs.
Students spend much of their experience working side-by-side final-year Iowa student pharmacists completing clinical rotation experiences in the Iowa City area. A mix of inpatient and ambulatory care settings are included. Prior to attending clinical rotations, students meet with college faculty to receive preparation for the experience and the clinical approaches they will observe.
Currently, students from Keio visit in the fall which aligns with our normal fall semester, so Iowa students are on campus and a full calendar of events, activities, and major college sports are available. Students stay in a home-based Bed & Breakfast near campus.
Jay D. Currie,
Pharm.D., FCCP, FAPhA
Clinical Professor and Chair
Department of Pharmacy Practice and Science
College of Pharmacy
University of Iowa