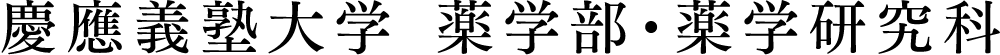2023年度
アドバンストレギュラトリーサイエンス海外演習
2023年9月23日~10月1日
高橋 侑伽(薬学部薬学科6年*当時)
私が最も印象に残っているのはWHOへの訪問です。WHOの日本人職員の方とお話させていただきましたが、彼女の上昇志向にはっとさせられる思いでした。具体的には、キャリア構築に対して貪欲な姿勢、また人との繋がりを大事にする姿勢です。彼女は、新卒で薬剤師の経験をされた後に、海外の大学でファーマコビジランスを学び、その経験と学びを活かして現在はWHOで働かれていました。日本の臨床現場で薬剤師という立場からWHOという国際的な機関へのキャリアチェンジは先例の少ないことで、難易度が高いうえに不安を伴うことだと考えます。しかしその方は、「WHOには臨床現場を実際に経験してきた職員が少ないため、自分のキャリアを強みにして働いている」とおっしゃっていました。
また、WHOにおいて日本人の職員が少ないというお話も伺いました。理由として、3か国語以上の言語を話せる人が限られていることが足枷となっているそうです。優秀な人材が言語力の欠如によってその能力を存分に発揮できない現実に、専門性と同等に言語力を磨くことの重要性を痛感しました。
これを読まれる皆様には、大学在学中にしかできない経験に貪欲にチャレンジしてほしいです。私は大学2年次にThai Pharmacy Program、また大学6年次にARSに参加させていただきました。海外の医療機関・規制当局・製薬会社・保健機関など、今後の人生において自身の海外旅行や仕事では訪問できないであろう場所にも足を運べる貴重な機会を得ることができました。新薬開発がグローバル化されている昨今の医薬品業界において、海外との関わりは切っても切り離せません。そのうえで、まずは視野を広くもち、他国をも含む人との協働を楽しむ余裕をもつための第一歩として、海外研修への参加が将来を考えるきっかけとなれば幸いです。


2023年9月23日~10月1日
佐野 みのり(薬学部薬学科6年*当時)
私はアドバンストレギュラトリーサイエンス海外演習に参加し、9日間にわたってワールドヘルス領域において活躍する企業、機関に訪れました。
研修は他ではできない貴重な経験でした。
特に、医薬品の研究、開発、製造のそれぞれの段階について、世界的な機関、企業において深く学ぶことができたことが良かったです。研修では疫学研究に大きく貢献するBioBank、製薬企業の工場の見学、それぞれの施設におけるレギュラトリーサイエンスに関連した講義の拝聴を行いました。自分で感じ、日本との違いや今後変えていくべき点などを考えて発信することで、知識を経験としてより深いものにすることができました。私は来年から薬局薬剤師として勤務しますが、本研修での経験を通じて視野を広く持って患者指導、薬局運営に関わっていくことができると考えています。
また、ランチタイムなどの講義以外の場において世界を股にかけ活躍している方とお話しできる機会がとても貴重であったと考えています。企業や団体としてだけでなく、一個人としての仕事に対する思いを聞くことができました。また、自分が目指す将来像を持ち、それに向かってするべきことを再認識する良い機会となりました。
少しでも興味がある学生は参加することをお勧めします。貴重な経験ができる事は勿論ですが、先生方のサポートのおかげで食事、宿についても安心して9日間を過ごすことができました。また、学年を超えて志が高く優秀な仲間と絆を築くことができたことも収穫だと考えています。



海外レギュラトリーサイエンス特別研修
2023年9月23日~10月1日
大川 拓眞(薬学研究科薬科学専攻後期博士課程1年*当時)
私は普段、免疫学系の基礎研究に従事しており、医薬品開発やレギュラトリーサイエンスとは縁遠いと感じていました。しかし、このプログラムを通じて、基礎研究者にも有益な経験であることを確信しました。この記事では、レギュラトリーサイエンスに馴染みの薄い基礎研究者として、プログラムで得た知見と今後の展望について述べます。
本プログラムはCOVID-19パンデミック以降初の研修であり、初の欧州での研修でした。行き先はデンマーク・コペンハーゲンとスイス・ジュネーブの2か国。コペンハーゲンではデンマーク医薬品局、バイオバンクシステムを管理する機関、2つの製薬企業、大学に訪問しました。また、ジュネーブではWHOと国際連合という世界的な機関を訪問しました。
各訪問先で得た知識や経験を通じて、医薬品開発、医薬品監督、企業の活動、国際機関の役割について広範な理解を得ることができました。この研修を通して、世界の情勢について包括的に学ぶ機会が得られ、通常の研究生活では得られない視点を開拓できました。例えば、バイオバンクという研究を支える根幹となる機関の現状と課題、医薬品局や製薬企業・WHOでの研究の発展の末、販売承認された薬をいかに管理していくかといった視点です。
最後に、研修に同行いただいた漆原先生、原先生、事前講義を担当いただいた大江先生、現地発表の準備に尽力していただいたFoster先生に深く感謝申し上げます。






2023年9月23日~10月1日
肥沼 佳菜(薬学研究科薬学専攻博士課程3年*当時)
私はかねてよりグローバルヘルス分野に興味があったため、海外で行われている薬学研究や国際機関の取り組みについて学ぶことのできる本プログラムに参加しました。
デンマークとスイスを訪問し、規制当局や製薬企業などの様々な施設を見学させていただきましたが、中でも世界保健機関 (WHO) での経験が印象的でした。WHO は "Health for all" を目的に設立された機関です。本プログラムでは、本来は関係者でなければ入ることのできない、ジュネーブのWHO本部に入る機会をいただきました。テレビでしか見たことのなかった会議室に実際に入ることができたことも感動的でしたが、WHOで働く日本人職員の方のお話を伺ったことが最も心に残っています。国際機関で働くためには自分の強みややりたいことを周囲にしっかりとアピールすることが必要なことや、アピールの場を得るためには周りのスタッフと日ごろからよくコミュニケーションを取り、自身のネットワークを広げるべきであることなど、実際に国際舞台でご活躍されている方から国際人に求められる資質をお聞きできたことは、私にとって大変大きな学びでした。
訪問先での講義や見学で新たな知識を得られたことももちろんですが、英語でプレゼンテーションをする力や積極的に質問する姿勢など、日本で学んでいるとなかなか身に付けることのできないコミュニケーションスキルを向上させることができた点で、本プログラムに参加して良かったと感じています。今後参加される方々もぜひ、自分の思いや考えをためらわずに表現し、実りある時間を過ごしていただけると嬉しいです。


2019年度
アドバンストレギュラトリーサイエンス海外演習
2019年7月17日~7月28日
中谷 友惟香(薬学部薬学科6年*当時)
2019年度のアドバンストレギュラトリーサイエンス研修に参加して感じたこと、今の仕事とのつながりについて、お話しさせていただきます。
私は、価値のある医薬品やその情報を届けることで、世界中の患者さんへの安心安全な薬物治療の提供に貢献したいという思いがあります。本研修は、医薬品開発について様々な視点での考えや姿勢を学ぶことができる貴重な機会であると思い、参加いたしました。
研修では、製薬企業やCRO企業、規制当局、治験実施医療機関、研究所などを訪問しました。各施設にて日本における医薬品開発や市販後調査などの安全性情報管理について紹介し、米国との違いを質疑応答から学ぶことができました。また、各施設での取り組みを伺うだけでなく、インターンシップ生との交流の機会があり、薬学教育の違いについても知ることができました。この研修で最も感銘を受けたのは、"Patient engagement"という考え方です。患者さんの意見や意思を傾聴し、治験に取り入れるだけでなく、患者さんや一般人へ治療や健康についての情報を発信することで、医療への正しい理解を促し、パブリックヘルスの向上を目指すという考え方だと感じました。本研修を通じて、患者さんの声に耳を傾けるという姿勢を大切にし、世界中の患者さんにより良い医薬品や情報を届けるという「ひたむきな情熱」を持ち続けたいと思うようになりました。
現在、私は製薬企業のファーマコビジランスという仕事に従事しています。ファーマコビジランスでは、患者さんの安全を確保するために、安全性情報を収集、評価し、新たなリスクの懸念が発生していないか、注意喚起や情報提供をする必要がないかを検討します。市販後だけでなく、開発段階からも関わり、市販後の安全性監視活動、リスク最小化策について検討します。医薬品の有効性とリスクは表裏一体ではありますが、開発段階から市販後にかけて、医薬品の一生を監視し、必要な情報を発信することで、医薬品のベネフィットバランスを保ち、患者さんの安全性を守る使命があります。
ファーマコビジランス業務に携わり約3年が経ちましたが、安全性情報の評価方針や対策検討に迷った時は、本研修で学んだ"Patient Engagement"の考え方が心のよりどころでした。どのような観点で情報を確認するのが良いか、医療現場や患者さんにこの情報を届けないとどのような影響を及ぼすのか、社内で議論し、時には医師の先生方にご相談させていただき決断します。少し医療現場から遠い場所で安全性情報を確認していますが、すべては患者さんの安全性確保のための業務であることを忘れてはなりません。
医療現場や患者さんに私たちが伝えたい情報が届き理解されているのか、医薬品の適正使用にあたる行動変容につながっているのか、把握しきれない現状があると感じています。この解決方法も、しっかり医療現場や患者さんの声に耳を傾け、患者さんもチームの一員として捉えて解決していくことが良いのではと私自身は考えます。"Patient Engagement"は新しい考え方のようで、双方のコミュニケーションを重視する、つまり製薬会社の一方的なコミュニケーションにならないよう、基本的で大事な考えだと感じています。今後もPatient Engagementの考え方を胸に、患者さんや周りの方々の生活の支えになる情報を届けていきたいです。
本研修は医薬品開発だけでなく、医療を提供する上で大事な考え方や姿勢を多角的に感じ取ることができる貴重な機会だと感じました。一度に多くの施設に訪問できる機会はなかなかないですし、参加に迷っている方がいらっしゃればぜひ勇気を出して参加されることをお勧めします。きっと社会人になっても大事なよりどころとなるものをきっと感じ取れることと思います。
本研修にて多くのことを伝えてくださった企業や施設の方々、貴重な機会を設けてくださった慶應義塾大学の先生方に深く御礼申し上げます。



【関連Webサイト】
MIRAI PORT
前編:https://www.mirai-port.com/people/5084/
後編:https://www.mirai-port.com/people/5475/
2019年7月17日~7月28日
冨沢 佳弘(薬学部薬学科6年*当時)
本記事をご覧になっている皆様、はじめまして。2019年度のアドバンストレギュラトリーサイエンス海外演習に参加しました冨沢佳弘と申します。
私が本プログラムを修了して感じた、本プログラムの特徴や学んだことなどについてお話いたします。
本プログラムの一番の特徴は、「製薬業界のバリューチェーン」に関して、「世界を先導する」レベルで学べる点です。製薬業界のバリューチェーンは、企業やアカデミア等における基礎研究から始まり、企業や病院での臨床研究・開発、規制当局によるレビュー・承認、医療機関での医薬品等の使用、企業や規制当局による市販後モニタリング活動などがありますが、それらをリードする世界的な機関を訪問し、そこで活躍する第一線の研究者・実務家からうける講義やディスカッションは非常に勉強になりました。また、大学では、これらのピースは個別的に勉強され、ピースの関連性を俯瞰することは少ないですが、本プログラムを通じてこれらの多様なステークホルダーの有機的なつながりをリアルに体験し、理解を深めることができたことは、非常に有意義でした。
私は、同時期に「海外アドバンスト実習」にも参加していましたので、その両方を踏まえてのお話もいたします。本プログラムは薬をいかに「生み出す」かに主眼が置かれているのに対し、海外アドバンスト実習は薬をいかに「使う」かに主眼が置かれているという大きな違いがありますが、その両方の知識を持っている必要があると感じたのが、双方のプログラムを選択した理由です。実際に、国際的な目線で薬を「生み出す」側と「使う」側の両面を学べたことは、非常にプラスであったと、社会人となった現在も確信しています。もし、双方のプログラムに興味がある方がいらっしゃれば、参加してみることをおすすめします。
本プログラムに興味を持っている方、応募を迷っている方へ。慶應義塾では、国際担当の教職員の方や本プログラムに参加した先輩など、多数の方が皆様をサポートしてくれます。是非とも、参加を検討する中で、様々な方から情報収集し、納得のいく選択をしていただければと思います。私も、一人の塾員として応援しています。