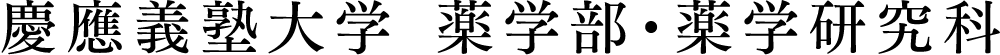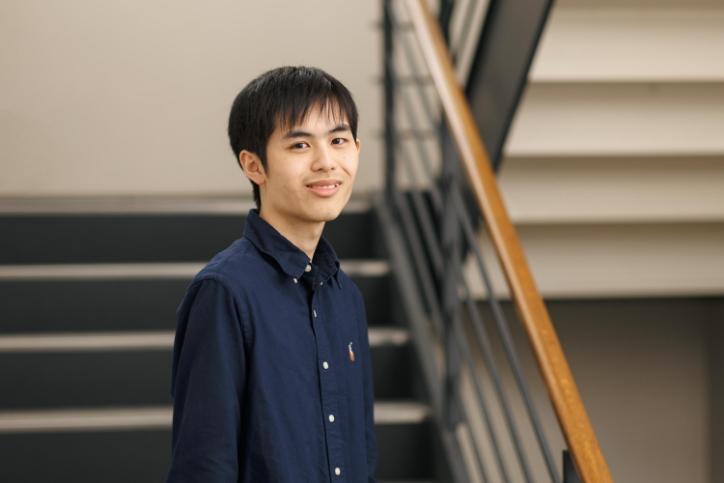
なぜ?と思う好奇心が原動力。
慶應薬学部で、有機化学を究めたい。
中学、高校と化学部に所属し、上級生の実験に感動。
それをきっかけに、有機化学の楽しさに目覚めて、薬学を志しました。
薬学の勉強は、それ自体が興味深く、大変ではあるけれど、
自分の知的好奇心が満たされて、充実した学生生活を送っています。
慶應義塾大学薬学部をおすすめしたい理由は、施設の充実と
学生の自主的な学びを全力でサポートしてくださる先生方。
ここは、有機化学を究めたいという私の願いが叶う場所です。
薬学部薬科学科2年
三橋 琉人(ミツハシ リュウト)
(2024年12月現在)
*課外活動について2025年10月現在(薬科学科3年)の情報を加筆しています。
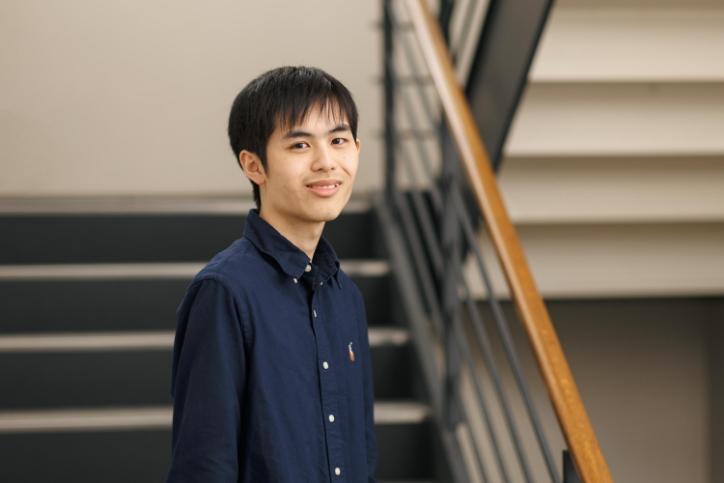
まるで魔法!化学部での上級生の実験を見て感動。
有機化学にハマり、深く究めたくて、慶應薬学部へ。
もともと化学が大好きで、中学、高校と化学部に所属していました。上級生の実験を見て、まるで魔法のようだと感動したことを今でも憶えています。高校生の頃には私自身も、有機合成の実験をしていたのですが、自分の手で分子を組み合わせて、意図した通りに合成できた時、何物にも代え難い喜びを感じました。有機合成は、見た目は地味かもしれません。「透明な液体を混ぜ合わせて何時間も色々な操作をしたら黄色い結晶が得られました」みたいに、全く知らない人から見れば一体何が面白いのか、と思ってしまうかもしれません。しかし、私は自分で何かを創る喜びを通じて、まるで魔法を唱えるような感覚が得られ、有機化学の楽しさに目覚めました。日々読んでいた教科書には、まるでファンタジーの魔導書を読むようなワクワク感がありました。
有機化学や有機化合物について学びたいと考えた時、学部の選択肢は、薬学部の他にも理工学部や農学部などいろいろありました。しかし、有機化合物の持つ性質を深く学ぶことができるのは、有機化合物を生体内で認識、代謝される薬として活用するために、分子を立体構造で捉える必要がある薬学部だと考えました。そして、薬学部の中でも知名度が高く研究活動も活発な慶應なら、将来の選択肢が広がるのではないかと思い、慶應義塾大学薬学部薬科学科に進学しました。
覚えることが多いと感じる、薬学の勉強。
しかし、観察と工夫でどうにかなるもの。
薬学部に入学する前、有機化学を勉強できる楽しみがある反面、心配が一つありました。それは、薬学部は単純暗記が多いという噂です。しかし、入学後に気がついたのは、単純暗記が多いと言われがちな薬学部ですが、意外にも科目と科目のつながりが強く、科目への深い理解があれば単純暗記の量を大きく減らせ、面白みも増すということです。だから、私は薬学で好きな科目を一つ見つけることをおすすめします。私の場合は有機化学でしたが、特に有機化学は各科目の基盤であり、ほとんどの科目につながっていますから、得た知識をいろいろ活用できておもしろい上、理解の効率も高まります。
確かに覚えることは他の理系学部と比べ多いと思われますが、私は2年間学んでみて、工夫次第で意外とどうにでもなるものだ、と思っています。
工夫の一つが、薬の名前の覚え方。薬の名前だって人間がつくった言葉ですから、当然、語源があります。名前を分解して、構成する要素を一つずつ調べていくと、由来と意味がわかります。そうすると、初見の薬でも構成要素からなんとなく効果効能が思い浮かびます。この話を講義で先生から伺って以来、暗記がずいぶん楽に感じるようになりました。
暗記する努力は大事だと思います。でも、「なぜ?」と思う知的好奇心を忘れないことはもっと大事。初めて見る薬に対して、鵜呑みにせずに「どうしてこういう名前をつけているんだろう?」と思えば、新たな学びが得られます。薬学部でこそ「なぜ?」と必ず思って、自主的に調べる姿勢は活きますし、大きく成長できると思います。

学生の自主的な学びを先生方が協力してサポート。
ありがたいと感じる、薬学部の環境。
薬学部に入ってもう一つ気づいたのは、学生が自主的に学ぶことに対して、先生方がとても協力的だということ。例えば、私は有機金属化学が好きだという話をある先生にしたところ、先生は「この本を読んだらいいよ」とおすすめの本を選んで貸してくださいました。また、ある先生の講義が白熱して、話が広がっていったことがあり、私が本来の内容とは違う質問をしたのですが、先生は次の週までにきちんと調べて、回答を準備してくださいました。こうして学生の学びに対して、先生方が全力でサポートしてくれる環境は本当にありがたいと感じています。
漢方部に所属して、課外活動も充実。
課外活動では、薬学部漢方部に所属しています。漢方部では、その名の通り、漢方について勉強したり、植物園の見学をしたりします。合宿では慶應の施設である赤倉山荘に宿泊し、妙高高原の植物を観察しました。それだけではなく他の東洋医学の領域にも踏みこんでいます。先日は、鍼治療の体験会を開催しました。東洋医学が基礎を置いている生薬の中には、有機化学的に分析すると、構造式と作用に関連が見られたり、有機合成の対象にもなったりして、有機化学の視点から見ても、とても興味深いです。
3年生になった現在、私は副部長となり、部の勉強会の資料作成等勉強方面を担っています。

そのための環境は、整っている。
受験生のみなさんは今、きっと勉強を楽しむ余裕などないと思います。でも、大学に無事入学したら、点数や成績を効率良く上げようとか、そういうことではなくて、ぜひ自分が「なぜ?」と思うことを突き詰めて学んでほしいです。
慶應薬学部には薬学メディアセンターと呼ばれる図書館があって、大量の蔵書が読めますし、メディアセンターにない本でもオンラインで読める場合があります。私は、よく閉館時間までメディアセンターにいます。疑問に感じた事を即座に調べられるという意味でも、探していく過程で様々な本と出会い周辺知識の理解が深まるという意味でも魅力的な場所です。慶應には学びをサポートしてくださる先生方や充実した設備など「なぜ?」を追究する環境が整っています。