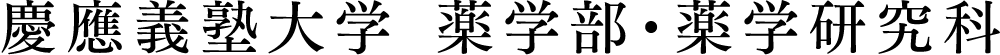セルフケアによる健康寿命の延伸。
その啓発に適任なのが、薬局です。
膨らみ続ける医療費の削減は、現在の日本の最重要課題だと言えます。
国も自治体も財政ひっ迫を訴える今、解決策として注目されているのがセルフケア。
予防や早期発見に努める、軽医療はOTC医薬品(市販薬・大衆薬)で済ませる、といった習慣が個人に
根づけば、医療費を本当に必要な人々に回すことが可能になります。
こうしたセルフケアによる健康維持、もしくは健康寿命の延伸において、
啓発役として最もふさわしいのが、薬局です。
慶應義塾大学薬学部には「健康サポート薬局」として認定された附属薬局があり、
地域住民の健康増進と薬学部生にとっての実践教育という二つの役割を果たしています。
医療薬学・社会連携センター 社会薬学部門 教授
山浦 克典(ヤマウラ カツノリ)
(2023年12月現在)

患者さんが薬物治療を継続するうえで妨げとなる諸問題を、医療制度や構造、
薬や健康に対する患者の認識や価値観、行動に影響を与える要因を
分析し解決を目指すのが、社会薬学。
医師や看護師、薬剤師などの医療従事者から患者さんへ提供される医薬品が、正しく効果を発揮できるかどうかは、患者さんを取り巻く社会の制度や構造にかかっていると私たちは考えます。
例えば、新型コロナウイルスによるパンデミックが発生した頃から現在まで、咳止めや解熱薬が入手しにくい状況が続いています。患者さんに処方したくとも薬自体が流通していない。こういう現象は今まで起きたことがなかったと思います。また、メディカルダイエットと称して医療用医薬品を痩せるために使う不適切使用が横行することで、薬を必要とする患者への供給不足が医療現場で起きています。あるいは、麻薬や覚せい剤を使用した時のような多幸感を得ようとして、OTC医薬品を大量・頻回に服用(オーバードーズ)する若い世代の増加が問題となっています。これらの問題は、医療用医薬品の処方やOTC医薬品販売の規制緩和により、手に入りやすくなった影響もあると思います。
こうした薬への社会的影響を研究して、よりよい医療制度につながるようなデータ、あるいは政策提言を行うのが、社会薬学という学問です。セルフメディケーション税制という制度があるのですが、これは風邪などの軽い不調のときにOTC医薬品を購入して対処した人が、特例として購入費用について所得控除を受けることができる制度です。これも、医療費を本当に必要な患者さんのために使うようにするにはどうすればいいか、という課題に対する制度上の解決策です。

現在取り組んでいる研究は「セルフケア」と「口腔ケア」。
その両方の鍵を握るのが「健康サポート薬局」の存在。
私が現在、特に注力している研究分野は二つあり、その一つがセルフケアです。日本人の平均寿命は男性81.41歳、女性87.45歳ですが、健康寿命は男性72.68歳、女性75.38歳で、それぞれ約9年、約12年の開きがあります(※)。健康寿命を延伸するには、国民一人ひとりが疾病の予防・早期発見に努めるセルフケアが有効であり、その啓発役として最も適しているのが、薬局です。一般的に、医療提供施設の多くが何らかの疾病や怪我があって初めて訪れるのに対し、薬局へは常備薬やサプリメントを買いに行くなど、健康な人でも気軽に立ち寄ることができます。
薬局の中には厚生労働省が定める一定の要件を満たした「健康サポート薬局」というちょっと特別な薬局があり、所定の研修を修了した薬剤師がいて、薬のことの他にも食事や介護など幅広い相談ができます。全国には約6万店の薬局がありますが「健康サポート薬局」を標榜するのは現在わずか3千店ほど。その数少ない中に、慶應義塾大学薬学部附属薬局も含まれます。これからのセルフケアの時代にあって、附属薬局の役割は大きいのです。
私が注力しているもう一つの研究分野は、口腔ケアです。歯周病はギネスブックにも「世界で最も患者の多い病気」として記載されていて、成人の約7割が歯周病を患っていると言われています。じつはこの歯周病、全身疾患の増悪因子になるというエビデンスが集まっており、脳梗塞や糖尿病、心筋梗塞、認知症などに影響を与えます。特に糖尿病患者で歯周病を持っている人は非常に多く、歯周病を治療すると糖尿病の数値が改善することも知られています。
ただ、歯周病の解決すべき問題は症状がわかりにくく、予防もあまりされていない点。歯科医院へ駆け込むのは、かなり悪化してからです。そこで「健康サポート薬局」を中心に、全国の薬局が歯周病の定期健診や口の中の健康管理について効果的に啓発できれば、口腔ケアの観点からも健康寿命の延伸に貢献できます。
※出典:厚生労働省「令和元年簡易声明表の概況」「健康寿命の令和元年値について」

大学構内にありながら、地域住民の方々に利用される唯一の薬局。
慶應の附属薬局は、地域貢献と教育の大きな意義を持っている。
附属薬局は、大学附属でありながら「健康サポート薬局」として周辺地域の方々の健康増進や医療に貢献できるという非常に特殊な立ち位置にある施設です。無菌製剤室を備えるなど設備面でも優れていて、近隣の薬局からの求めがあれば、この無菌室を利用していただくことが可能で、この点においても地域医療のサポートに貢献しています。
また、大学施設ですから、教育面でも大きな役割があります。薬学系大学は日本に今、80校以上が存在しますが、附属薬局を持つ大学はわずか5%程度です。しかも、大学構内の教育施設として設置され、実際に地域の患者さんにも利用していただいている薬局は、日本では慶應義塾大学薬学部附属薬局、ただ一つです。近隣住民の方が訪れる場所でありながら、学生も教員も自由にアクセスできる点が最大の特徴だと言えます。慶應薬学部の場合、附属薬局が構内にあるので、薬剤師としての実務経験がある教員が、講義のあと白衣に着替えれば薬局で臨床の薬剤師として仕事ができるわけで、この常に実臨床に触れられる環境が、学生に臨場感をもって知識を伝えたり知見のアップデートに大きく役立ちます。
一方、学生にとっても、学内で行う実習を附属薬局で行うことのメリットは大きいです。模擬患者を相手に薬の説明をする実習でも、カウンターの隣では本当の患者さんと薬剤師がいるわけですから、臨場感と緊張感を味わうことで薬剤師としての心構えができてきます。実習を受けた学生からのアンケートを見ると、実際の業務をリアルにイメージできて良かったなど多くの好意的な声が寄せられていました。


薬剤師の役割が拡大する今は、逆に世の中に知ってもらう好機。
さらに患者さんに寄り添う、新たな薬剤師をめざしてほしい。
2020年に施行された改正薬剤師法により、薬剤師の責任の範囲が少し拡大しました。今までは患者さんに薬をお渡しする際に説明するところで業務は完了でしたが、現在は患者さんがお渡しした薬を服用している間も必要に応じて使用状況の把握や服薬指導を行う義務を負っています。この服薬期間中のフォローアップ義務化により、薬剤師はより忙しくなると思いますが、これは薬剤師の仕事を世の中に広く知ってもらうためのチャンスではないかと捉えることもできます。
さらに患者さんに寄り添う、この新しい薬剤師像に魅力を感じた皆さんには、ぜひ慶應薬学部で学んでいただき、社会に貢献したいという思いをしっかり胸に抱きながら、将来薬剤師の領域を先導する人材に育っていただきたいと思います。
また、慶應薬学部は、学び得た薬学の知識と技術を活かして、薬剤師だけでなく研究者や製薬企業、行政など多様な進路を選ぶことができます。そのことを可能にするのは、本学が最先端の領域にいる研究者と、医療系の臨床経験を積んだ教員の両方が揃っているからで、薬に関心を持つ皆さんが自分の未来をどのように思い描いたとしても、きっとその思いに応えることができると思います。