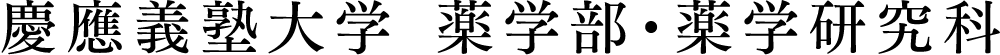【座談会後編】
失敗を失敗のままにしないで。
そこから学び続ける姿勢が、
自分の将来を切り拓いていく。
慶應薬学部薬学科(6年制)の学生にとって、薬剤師は関心の高い進路です。
今回の座談会の進行役である郷さんは、
現役薬剤師・元薬剤師のお二人に病院薬剤師と薬局薬剤師の違いについて、訊いてみました。
その答えには、患者さんとのそれぞれの向き合い方が反映されていました。
また、「失敗を怖がりすぎてはいけない」という一言から、
参加メンバーの失敗談トークへ。その結論は、勇気をもらえる内容でした。

左から、郷さん(在学生)、杉本さん・松浦さん・三浦さん(卒業生)、地引助教(教員)
参加者の所属・インタビュー内容は取材当時(2024年3月)の情報です。
THEME 01
病院薬剤師と薬局薬剤師の違いとは
郷 1年生の授業で、病院と薬局の見学が1日ずつ予定されていたのですが(早期体験学習)、病院には新型コロナウイルスの影響で行けなくなってしまって。本来なら、それぞれの実習で病院薬剤師と薬局薬剤師の違いがつかめたはずなのですが、それができませんでした。この違いについて、現役薬剤師の三浦さん、薬剤師の経験をお持ちの地引先生にぜひお話を伺いたいです。
三浦 私には病院での経験しかありませんから、病院側としての見解をお伝えすることになりますが、やっぱり注射薬を扱うかどうかが大きな違いだと思います。今は在宅医療が普及していて、注射剤のミキシングに関わっている薬局は増えていると思いますが、病院の方が頻度は高いです。あとは、医師、看護師などさまざまなコメディカルと直接やりとりする機会も、病院の方が多いですね。一方、一人の患者さんやそのご家族とかかりつけとして長く関わっていくのが、薬局薬剤師ではないかと思います。
郷 関わる人たちやその関わり方にも、かなり違いがあるんですね。
三浦 慶應義塾大学病院の場合、短期間入院の患者さんが多いんですね。繰り返し入院される方とは、ある程度顔見知りになることもありますが、ほとんどは短期間の関わりになってしまいます。もし、同じ患者さんと長く関わりたいと思うのなら、薬局薬剤師が向いているのではないでしょうか。
地引 病院薬剤師と薬局薬剤師の違いは、三浦さんのお話の通りだと思います。カルテを見ながら、いろいろな医療専門の職種とコラボレーションするのが、病院薬剤師。薬局薬剤師の場合も、多くの職種と関わる機会はありますが、組織内ではなく地域でのコラボレーションになるのが違いだと思います。ただ、患者さんとのコミュニケーションは基本的に同じです。
郷 地域とより密に関わるのが薬局薬剤師なんですね。
地引 そうですね。地域の中で、保健活動と薬物治療を担当するのが、薬局薬剤師ですね。
郷 町の薬局には行く機会がありますが、私は幸運なことに入院した経験がないので、病院薬剤師のことがあまりわかっていなかったんです。今日はお話が聞けてよかったです。
三浦 郷さんは、5年次の病院実習で特にやってみたいことはありますか?例えば、患者さんへの服薬指導ですとか、調剤を体験したいですとか。私は学生を受け入れる側なので、参考までに聞いてみたいです。
郷 調剤は大学でも練習ができそうなので、病院ならではの体験として、患者さんへの服薬指導に関心があります。少し不安もありますけど...。

THEME 02
企業と患者さんの接点
郷 製薬会社勤務の杉本さん、医療機器メーカー勤務の松浦さんは、実際に患者さんと会ったり話をしたりする機会はあるんでしょうか?
杉本 臨床開発モニターを担当していた頃は、医療機関を訪れることが多く、そこでカルテを拝見する機会はありました。目にしたカルテに、私が開発している新薬を使ったことで、患者さんの身体の調子がとても良くなった、と書かれていたことがあって。そういう文字を読むだけで、嬉しかったです。患者さんに直接お会いすることはないですが、お使いになった際の効果や感想は何らかの形で届きます。そうした患者さんの声がモチベーションになっていますね。この点は、薬剤師も製薬会社も同じだと思います。
松浦 私は薬科学科(4年制)出身なので、薬剤師資格は持っていません。ただ、杉本さんと同じように、自分が開発に携わった製品を使った感想がマーケットからのフィードバックとして届きます。もしくは、試作品の使用感をユーザーの方々にヒアリングする機会はあります。そういう場で、こうした方が使いやすい、こういう機能があったら便利なのに、といった声をいただくと、それが研究開発のモチベーションにつながりますね。
郷 患者さんとの関わりは、企業でもあるんですね。直接的か間接的かという違いはあるにせよ、患者さんの声がやりがいにつながることはよく伝わってきました。
一方で、私は直接患者さんと接することに少し怖さも感じます。患者さんの苦しみを目の当たりにすると、その場から逃げてしまいたくなりませんか?
三浦 初めて自分一人で患者さんに薬の説明に行った時は、その患者さんの治療の責任が私にかかってくるので、その点はやっぱり怖いと思いましたね。あるいは、医師からの問い合わせに対して、自分が処方内容を提案した場合は、責任を感じますし。うまく行かなかったらどうしようという不安も、今回の内容は少し違ったのかもという反省もどちらもあるんですが、そういう経験の積み重ねが自信につながっていくのだと思います。若い頃の試行錯誤は絶対必要ですよ。
郷 失敗をあまり怖がりすぎてもいけないんですね。

THEME 03
失敗からしか学べないことがある
郷 皆さんの失敗談をお伺いしてもいいですか?
地引 失敗がありすぎて、どれを話せばいいのやら、という気分なのですが...以前、治験に参加された患者さんをすごく怒らせてしまったことがあります。その時は、治験の患者さんの気持ちに寄り添えなかったかもしれないと反省しました。治験の場合、世の中でまだ販売されていない薬で治療しているわけですから、もしこの薬が使えなくなったら...と考えてしまうのは当たり前です。だから、ちょっと感情が不安定な日だってあるはずで。そこを汲み取ってあげられなかったのが、当時の私だったと思います。
郷 そういうことがあっても、地引先生はめげないんですか?
地引 最終的に患者さんに感謝されることが最大の労いになります。辛いことがあっても、感謝の言葉一つで、すぐにまた頑張ろうと気持ちを立て直せるので。そういう仕事に出会えて良かったと思います。
杉本 複数病院の治験を担当していた際に、病院に期日までに作成し送付する資料が多く、余裕をもって対応できず、宅配便や郵便では間に合わないのでバイク便を手配して即日で届けてもらったことがあります。一度失敗した時に、次は同じ失敗をしない、うまく行くように対策を考えようと発想することが大切なんだと思います。だから、小さな失敗なら、若いうちにたくさんしておくべきです。失敗を反省して、先回りして考えられるようになればいいんですから。
松浦 治験品を出荷する段階で、私のミスからアクシデントを一つ起こしてしまって。このままでは、提携先の企業の方にも迷惑をかけてしまう状況の中で、生産現場のベテランの方が長年の経験に基づく対策を提案してくれて、それでピンチを脱しました。会社の仕事は、多くの人とチームを組んで進めていくことがほとんどです。治験品出荷のトラブルは私が社会人1年目の時のことでしたが、自分が助けてもらったこの経験を活かして、もし今後、周りの誰かが失敗した時はリカバリーしよう、そういう経験を培っていこうと決めました。失敗から学ぶことは、若いうちなら許されます。若いうちに失敗した方が、自分の成長にはつながると思います。
郷 失敗には、すごく悪いイメージがあって、私は何か失敗するとすぐに落ち込んでしまいます。でも、失敗から学ぶ、学び続けていく姿勢がキャリアアップにつながるんだと思いました。失敗って、決して悪いことばかりではないんですね。