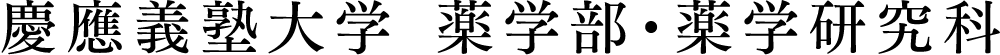【座談会前編】
慶應薬学部だからこそ広がるキャリアパス。
考えて選ぶことの豊かさ。
慶應義塾大学薬学部・大学院薬学研究科の学生数の内訳は、
男子46%に対し女子54%(※2024年4月現在)。少しですが、女子学生の方が多くなっています。
このような現状を踏まえて今回、女性の卒業生・教員・在学生の皆さんに
女性の視点から薬学部出身者のキャリアパスについて、さまざまな角度から話し合っていただきました。
また、後半では、在学生からの関心が高い結婚・出産といったライフイベントが話題となりました。

左から、郷さん(在学生)、杉本さん・松浦さん・三浦さん(卒業生)、地引助教(教員)
卒業生
杉本 麻衣子(すぎもと まいこ)
薬学部薬学科 2013年卒。在学時は薬剤学講座所属。協和キリン株式会社勤務。同社入社時は臨床開発モニターとして治験への協力を医療機関へ打診・依頼する等の業務を担当。現在は、治験計画の策定にあたっている。2023年に第2子を出産し、産休を経て、2024年春、復職。
卒業生
松浦 みなみ(まつうら みなみ)
薬学部薬科学科 2012年卒。薬学研究科薬科学専攻修士課程 2014年修了。テルモ株式会社勤務。同社に籍を置き、社会人学生として薬学研究科薬科学専攻後期博士課程入学、2019年修了。在学時は創薬物理化学講座(現:創薬分析化学講座)所属。医薬品と医療機器を組み合わせたコンビネーションプロダクトによる新たな治療法の研究開発に携わる。現在は育児休業中でアメリカ在住。
卒業生
三浦 あす美(みうら あすみ)
薬学部薬学科 2015年卒。在学時は生化学講座所属。慶應義塾大学病院薬剤部勤務。女性病床の病棟薬剤師を担当したことがきっかけで、妊婦・授乳婦の方々の薬に関する問い合わせを多く受けることになり、これを機に妊婦・授乳婦薬物療法認定薬剤師の資格を取得。
教員
地引 綾(じびき あや)
薬学部助教(医療薬学・社会連携センター医療薬学部門)2014年着任。明治薬科大学薬学部卒業後、千葉大学大学院を経て、2005年から2014年まで筑波大学附属病院薬剤部にて薬剤師として勤務。千葉大学大学院薬学研究院では高齢者薬剤学研究室に所属。以来、女性特有の更年期障害に関する研究を続けている。
在学生
郷 沙智子(ごう さちこ)
薬学部薬学科2年。本座談会の進行役を務める。課外活動として、芝学友会、芝大門茶道部に所属。慶應薬学部を選んだ理由は、生物学や薬学にもともと興味があったのに加え、薬剤師という国家資格の安定性に惹かれて。将来の進路は、公務員に関心を持っている。
(2024年3月現在)
THEME 01
慶應薬学部にして良かったと思うこと
郷 本日、進行役を務めさせていただく薬学科2年の郷沙智子と申します。よろしくお願いいたします。
まず初めに、先輩方にお伺いしたいのが「慶應薬学部を選んで良かったこと」です。いかがですか?
三浦 以前、医療系三学部合同教育の授業を一緒に受けていたドクターと病棟で再会したことがありました。お互い「久しぶり!」と言い合って。その方と同じ患者さんを担当していたので、実際の現場で意見交換できた時は、三学部合同教育の意義を実感しました。大学受験の時も、薬学部だけの単科大学よりも複数の医療系学部を擁する総合大学を希望していたので、自分の選択は間違っていなかったと思えました。
郷 三学部合同教育の授業って、記憶に残っているものなんですね。私は今、三学部合同教育の実行委員を務めているので、合同教育で知り合ったエピソードを聞くと嬉しくなります。
杉本 私が慶應薬学部を選んだのは、薬剤師以外の選択肢も考えられる大学だったからです。実際、就職活動の時期には周りに開発職を目指す人がとても多くて、私にとって心強かったですね。在学中、一番辛かったのは就活で、何社も落ち続けて心が折れていた時期がありましたが、同じ志を持つ仲間がたくさんいて、お互い励まし合ったり、情報交換し合ったりすることで乗り越えることができました。私が現在勤めている会社に後輩がコンスタントに入ってくるのも、慶應義塾ならではだと思います。

松浦 私の場合は、ものづくりがしたいということと、医療が学びたいと思いつつ化粧品にも興味があったので、幅広い学びができる大学をと考えて、慶應薬学部を選びました。それに、慶應が文武両道の精神をすごく大事にしているところにも私は好感を持っています。私は中学・高校で陸上部だったので、慶應義塾体育会の競走部に入ったのですが、体育会にはいわゆるオリンピック選手もいれば、その競技が好きだから続けたいという人もいました。いろいろな人・価値観があって、そういう環境で大学生活を送れたことは自分の財産になっています。卒業後も集まる機会があって、いろいろな話を聞くと、今でも自分の視野が広がっている実感がありますね。
郷 いろいろな学部があって、いろいろな人がいて。慶應義塾には「広がり」を感じますよね。私も、その広がりに惹かれました。薬学部卒業生で組織する「KP会」もありますし、さまざまな価値観を持つ人同士の強くて広い絆を感じます。幅広い働き方が選択できるのも慶應ならではだと思います。
松浦 慶應薬学部で良かったと思うことは、もうひとつあります。私は今の会社に籍を置いたまま、社会人学生として博士課程に進んだのですが、この選択は自分にとって良かったと思っています。進学した理由は、入社後配属された研究開発チームと自分にギャップを感じたからでした。そのチームは多数の方が博士課程出身。仕事でトラブルが起きたら解決策を考え、トライする。ダメならまた別の解決策を考えて、というサイクルを回すことをみんな自然とできるんです。当時できなかった私は、自分の力不足を感じて、博士課程に進んで研究に身を置くようになれば、みんなと同じような思考ができるかもしれないと考えました。今もまだトレーニング中だと自分では思っていますが、博士課程を修了して、研究開発に携わるための素養は身についたと感じています。

THEME 02
慶應薬学部出身者のキャリアパス
郷 皆さんから就活の話、職場の話が出たところで、転職について、お伺いしたいです。私はもともと安定志向で、将来は安定した職に就ければと考えています。今は公務員に興味を持っているのですが、インターンの機会が少ないのが悩みの種です。港区や国税局で短期非常勤職員として働かせていただきながら、公務員ってこういう仕事なんだ、大きな資本を使って社会に貢献する仕事ってやりがいがあるなといろいろ学んでいるところです。公務員の仕事と自分が興味を持っている薬学の分野をからめていけたら、一生をかけて取り組みたい仕事になるのかもしれないと思っています。
地引 2年生でそこまで考えられるのは、すばらしいですね。国家公務員も視野に入っているのですか?
郷 PMDA(独立行政法人 医薬品医療機器総合機構)や厚生労働省、東京都にも関心があります。公務員のキャリアを積んだ後に民間企業に転職する方も多いと聞きます。ただ、私は転職についてあまりポジティブなイメージを持てていなくて。就職活動で大変な思いをするのに、数年後、それをまた繰り返さなきゃいけないと考えるとどうしても及び腰になってしまいます。皆さんは転職について、どんなイメージを持っていますか?
地引 このメンバーの中で転職経験があるのは私だけのようですが、会社員の経験はないんです。皆さんの会社では転職者は多いですか?
松浦 ここ数年、特に多い印象がありますね。仕事をしていると自分のやりたいことが変わるのは、誰しもあると思います。次のチャレンジがしたいと思って入ってくる人もいれば、同じことを思って出ていく人もいます。
地引 最近、転職サイトのCMがとても多いと思いませんか?今の世の中が、転職をポジティブに受け入れているのだと思います。もっとおもしろいことがしたいという気持ちの動きが自分の中で起こったら、その時が転職...キャリアアップという言い方がより適当かもしれませんが、そういうチャンスなのでしょうね。
杉本 入社前から、自分が働く完璧なイメージを持つのは難しいと思います。企業情報は頭に入っていたとしても、どういう仕事か、どういう職場かという正確な内容は入って初めてわかることなので。思っていたイメージと違ったと入社後感じる人が一定数いるのも当然という気がします。
松浦 私は、自由に転職できる業界は恵まれていると思います。製薬業界は、会社で学んで身につけた知識やスキルを確実に次に活かせますから、すごくいい環境です。
三浦 製薬会社も転職が多いと耳にしますが、実際多いものですか?
杉本 多いと思います。自分はどういう働き方がしたいか、それは働いてみて初めてはっきり見えてくるんだと思います。だから、最初の就職で「ここしかない」と決めなくてもいいのでは?

地引 杉本さんは意外と自分のイメージ通りだったんですね。今の職場で自分がやりたいことをできている実感はありますか?
杉本 ありますね。弊社は内資系の製薬会社ですが、やっぱり日本が中心となって、グローバルでの治験を実施したいとずっと思っています。
地引 日本から世界へ広げていくんですね?
杉本 そうです。世界へ広げていく活動に携われることがとても楽しいです。
郷 松浦さんは、入社前後でイメージのギャップはありますか?御社は特にグローバルビジネスが盛んな印象がありますが。
松浦 確かにグローバルな展開は多いですね。私自身は、入社3〜4年目で国際学会での発表や海外の方と一緒に仕事をする機会がありましたが、言語の壁、文化の壁があって、その時はプロジェクトを思うように進めることができませんでした。ただ、すごくいい経験になったので、次にそういう機会があれば、別のアプローチを考えて再挑戦したいと思っています。
THEME 03
薬学部出身女性にとっての結婚・出産

郷 今日、薬学部の先輩方にぜひお伺いしたかったのが、結婚や出産といったライフイベントについてです。私は薬学部薬学科(6年制)卒業後は今のところ大学院へ行くつもりはありません。理由の一つは結婚や出産のタイミングです。大学で6年費やすことについて、周囲から心配されたこともあり・・・。文系の学部は4年で卒業するのに、2年遅れると結婚や出産の時期が遅れてしまうんじゃないかと言うんです。私もその意見にちょっと影響を受けていて、学生の期間が長くなるほど、自分の思い描くライフプランの自由度が下がるんじゃないか、博士課程へ進めばさらに選択の余地が狭まるんじゃないかと不安に思ってしまって...。皆さんにはそういう不安や心配はありませんでしたか?
地引 私は30代後半で結婚したのですが、それまでずいぶん長いこと独身生活でした。大学院への進学や転職などありましたので。だから、結婚や出産が学生の頃に思い描いていたイメージ通りかと言えば、全くそうではありません。人生には、自分の努力さえあればうまくいくことと、自分の努力だけではうまくいかないことがあると思うんです。転職にしても、何で決まるかと言えば、タイミング。次へ行きたいという思いと自分のスキルの習得が揃って初めて、決まるものです。予定通りに進むことなんて全然ないけど、タイミングが訪れた時に自分が動けるように備えておくことは重要です。その時々で柔軟に動けるようにと考えている方がうまく行く気がします。将来のイメージが全く描けていなくても、今やりたいことをそのまま進めていれば、いいと思います。
三浦 2年間という時間が、学生の皆さんには長く思えて、もしかすると婚期が遅くなってしまうのでは、という気持ちはよくわかります。30歳過ぎてから結婚する人、24歳で就職して翌年結婚する人もいれば、仕事に集中して、結婚・出産は後にしようと考える人もいて、いろいろです。2年間を重く考えて心配しすぎなくても大丈夫じゃないかな、と個人的には思います。
杉本 私も、そう思います。私の夫は薬学部の同級生で博士課程へ進んだので、なかなか結婚できなかったんですよ。いつ修了するんだろうと待っていたわけですけど、私はその間、仕事がすごく楽しくて。まずは自分のキャリアを積んでいきたいと思っていたので、当時は子どもが欲しいとは思っていませんでした。夫の博士課程修了後に結婚して、程なくして子どもを授かって。いつがベストの時期なのか、その時になってみないと誰もわからないと思います。他人より2年遅くなる、博士課程ならプラス4年だと心配しなくても、その間、他に楽しいことがあって充実した時間が過ごせるかもしれない。ちょうどいいタイミングは、人それぞれなんだと思います。
松浦 私は、学部から大学院(修士課程)に進学し、計6年間在学しました。就職して、入社3年目で働きながら博士課程へ進み、3年間通いました。夫も、私の博士課程進学から1年後、同じように働きながら博士課程に進学し、その間に結婚して。お互いに、自分のやりたいことをやる生活をしていたので、結婚が自分のキャリアのハードルになるとは考えていません。ただ、出産は仕事に大きく影響を及ぼしますね。その期間は仕事を休みますし、子どもが産まれてからも仕事に全精力を傾けることはできなくなります。でも、仕事は何十年も取り組んでいくことですから。マラソンに例えるなら、出産・育児の時期はちょっとゆっくり走って、手がかからなくなったらまた全力で走ればいいと思っています。
郷 皆さんの意見を新鮮な気持ちで聴いていました。学生にとっては、中学は3年、高校も3年とだいたい3年単位で区切られてきたので、2年間長く在学することにハードルを感じます。でも、長い人生の中の2年間なのだから、そんなに不安に思わなくていいというのは、とても大きな発見でした。
地引 今回は価値観が似ている人が集まって話しているので、2年なんてあっという間という結論になるんですよね。将来、同じ価値観の人とパートナーとして出会えれば、問題ないかもしれないですね。