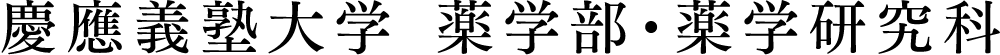憧れの研究者になる
目標に向かって。
一回り年上のいとこは、研究職。
高校生の頃、いとこから研究の話を聞くうちに、
自分も研究者になりたい、と思うように。
入学後は、長谷耕二先生の免疫学の授業に感銘を受けたことがきっかけで、
生化学講座に所属し、今は人工冬眠と腸内細菌について研究する日々です。
薬学研究科 薬科学専攻 修士課程1年
宮島 伶奈(ミヤジマ レイナ)
(2024年12月現在)

研究職のいとこが活躍している話を聞くうちに、
自分も研究職の道に進みたい、と考えるように。
私が薬学を志したきっかけになったのは、私のいとこです。彼女は私と年が一回り離れているのですが、理化学研究所の研究職に就いています。彼女から研究の現場の様子などをいろいろ聞くうちに、高校2年生の頃には、私も研究者の道に進みたいと思うようになりました。
数ある選択肢の中で慶應義塾大学薬学部薬科学科を選んだのは、絶対に研究者になりたいという強い思いがあったからです。薬科学科は学部3年から研究室に所属し、研究に没頭することができます。また、薬学の基礎知識を身につけた3年生の研究室選択時に、生物・物理・化学から自分の専門分野を選ぶことができます。この「専門は後で決められる」点が、じっくり考えて決めたい私にとっては魅力的でした。
免疫学の授業で聞いた母体のふしぎなシステムや
体質を決める腸内細菌に興味がわき、生化学講座へ。
今は、大学院薬学研究科薬科学専攻に進み、長谷耕二先生の生化学講座に所属しています。この研究室を選んだきっかけは、学部2年生の時に受けた長谷先生の免疫学の授業です。その内容は、自己と非自己の認識についてでした。例えば、母体にとって胎児は完全に自分の身体の一部ではありませんが、母体には胎児を攻撃対象としないよう制御する仕組みが備わっています。子どもの頃から当然のこととして受け止めていた現象に対して、「なぜ攻撃対象にならないのだろう」と疑問を抱いたことをきっかけに免疫研究に関心を持つようになり、それとともに生化学講座の研究内容にも興味を持つようになりました。
きっかけは、もう一つあります。長谷先生は授業の中でご自身の研究をよく紹介されていたのですが、その一つに腸内細菌に関するお話がありました。無菌環境で飼育されたマウスは、同じ餌を食べていても通常のマウスより太りやすいという結果が得られており、その違いを生み出していた要因は腸内細菌でした。
つまり、太りやすいか太りにくいかといった体質は腸内細菌によって決まるのだということです。この話が強く印象に残り、私自身も腸内細菌に興味を持つようになったため、長谷先生のもとで学びたいと考え、生化学講座を選びました。
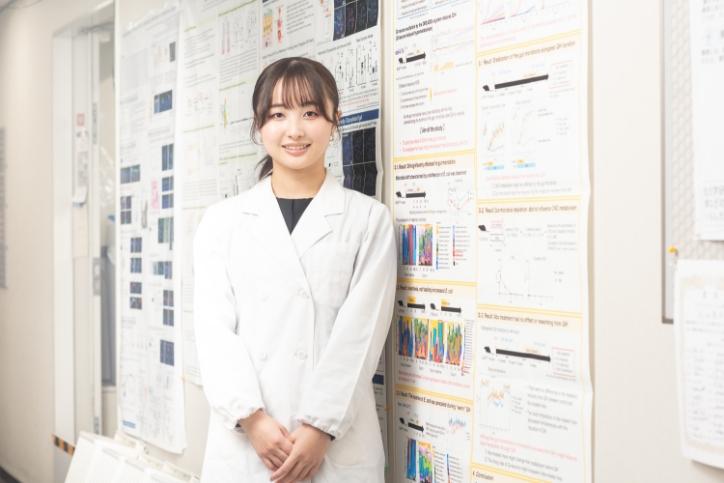
現在の研究テーマは、人工冬眠と腸内細菌の相互関係。
冬眠状態の中、菌はどう生き、眠りにどう影響するか。
現在の私の研究テーマは、人工冬眠と腸内細菌の相互関係です。2020年に、筑波大学と理化学研究所の共同研究として発表された論文で、Q神経の活性化により人工的に冬眠状態を誘導できることが明らかにされました。この論文に興味を持ち、人工冬眠が腸内細菌叢に与える影響を解明する研究が始まりました。
はじめに、人工的に冬眠を誘導したマウスから腸の内容物を採取し、冬眠下で腸内細菌がどのように変化するかを調べました。その結果、冬眠下では特定の細菌が著しい増減を示し、腸内細菌の構成が大きく変化していることがわかりました。さらに、この変化は冬眠の特徴の一つである低体温状態が強く影響していることも明らかにしています。
さらに研究を進めて、今は、腸内細菌が人工冬眠によってどう変わるかということだけでなく、抗菌剤を投与して腸内細菌をいったん完全に除去した後、人工冬眠の質、例えば体温の低下度合いなどが変わるかどうかを調べています。
生化学講座の特徴は、博士課程の学生が多いこと。高い専門性を備えていて、面倒見も良い先輩方のいる恵まれた環境で、具体的なアドバイスがもらえます。それに、1人1テーマ制なので、各自が全く違う研究を進めていて、ディスカッションの時もそれぞれ異なる視点から、いろいろな意見が出てきます。また、共同研究が多いところも特徴の一つで、私のように外部の研究機関や企業と連携して研究を進めている学生もいます。そのため、学内だけでなく学外の研究者とも交流する機会が多く、幅広い視点から研究を発展させることができる環境が整っています。
国際学会にて口頭発表とポスター発表を経験。
苦手な英語を1日3時間の努力で克服。
2023年9月に開催された「第21回あわじ感染と免疫国際フォーラム」で、口頭発表とポスター発表を経験しました。学部4年生にして初めての学会発表であり、さらに英語での発表だったため大きなプレッシャーを感じ、とても緊張しました。特に質疑応答では十分に答えることができず、自分の英語能力の不足を痛感し、悔しい思いをしました。
もともと私は英語が得意ではなく、所属している生化学講座は英語でミーティングを行うため、研究室に配属された当初から不安を抱いていました。しかし、この初めての学会発表をきっかけに、1日3時間を英語学習に充てるようになり、少しずつ力をつけてきました。最近では学会において外国籍の研究職の方とディスカッションができるまでに成長しています。
私にとって、英語への苦手意識はむしろ努力を続けるための原動力になっています。なりたい自分に近づくために克服すべき課題を明確にし、目標に向かって努力を止めないことが大切だと考えています。
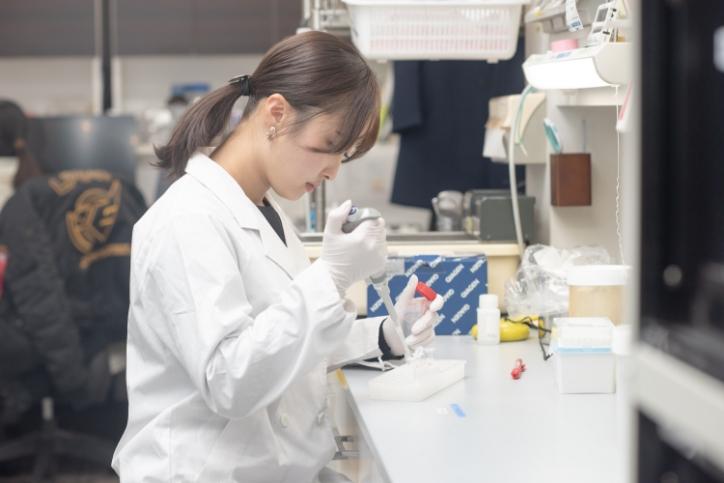
今も変わらない、研究者になるという夢。
いろいろな要素を考えながら、じっくり決めたい。
研究者になるという夢は今も変わりません。
企業が事業のための研究である一方、大学は基礎研究に重点を置いていると思いますし、自分が興味を持った分野を徹底的に研究できるのは大きな魅力だと思います。まだ、将来のビジョンは具体的ではないですが、自分のライフイベントやワークライフバランスといった要素も考慮しながら、じっくり考えて決めたいと思っています。